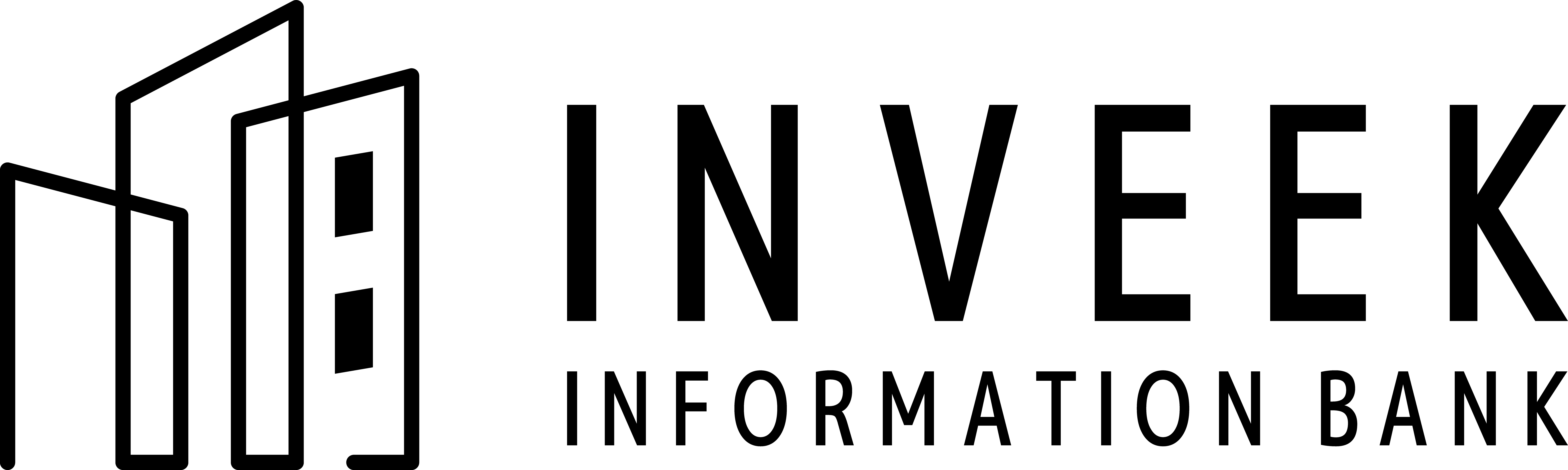金融資産は、株式や投資信託、現金・銀行預金を含めて実態がなくても経済的な価値を持つ資産のことです。契約上の権利で価値が保証されており、不動産をはじめとする実物資産とは異なり、売買が容易で流動性が高いです。金融資産は貯蓄・投資などを目的に、個人から法人まで幅広く保有されています。
本記事では、金融資産について実物資産との違いや、資産の種類を紹介します。年代・年収別の保有額など、気になるデータもあわせて解説。記事を読むことで、株や投資信託などの金融商品に投資するうえで、知っておきたいことがわかるようになります。
金融資産とは?

金融資産は、現金・銀行預金などのお金そのもの、株式・債券・投資信託などのお金に換えられる権利を持つ資産のことです。将来的に利益を得たり、今ある資産の価値を守ったりする役割があります。
例えば株式は、権利確定日に保有していれば、将来的に配当や優待を受け取る権利が得られます。インフレや為替変動から資産価値を守る目的で運用される投資信託は、長期的に資産を保全する効果を期待して購入されます。
金融資産は流動性が確保されている場合が多く、必要な時に現金に換えやすいことが特徴です。金融資産と対称的に語られることが多い資産が実物資産、金融資産に近い言葉では純金融資産があります。それぞれ詳しく違いを見ていきましょう。
実物資産との違い
金融資産は契約や権利として価値を認められていますが、物理的には存在しません。一方で、実物資産は土地や建物などの不動産、貴金属・骨董品など、実体のある資産を指します。
大きな違いは流動性の高さが挙げられます。金融資産は銀行・証券会社を通じてリアルタイムで売買できることから、最短であれば当日中、数日以内で取引が完了する場合が多いでしょう。一方で、実物資産は買い手を探すことからはじめる場合が多く、売買の完了に時間を要しやすいです。
また、金融資産と実物資産の価格変動を比較すると相関性がないことも多く、組み合わせて保有すればリスク分散が期待できます。リスクの少ないポートフォリオを形成するための分散投資を考えるにあたって、金融資産と実物資産の違いを理解して保有することが重要です。
純金融資産は住宅ローンなどの負債を差し引いたもの
純金融資産は、金融資産からローンなどの負債を差し引いた残りの金額のことです。例えば、現金・預金・株式・投資信託をすべて合計した金融資産総額から、住宅ローン・カードローンなどの負債を差し引いて純金融資産を計算します。
金融資産の保有量が多くても借入金が同等以上にある場合は、手元にある実質的な資産は少ないといえるでしょう。純金融資産がプラスで高い水準にあるほど、経済的に余裕があると判断できます。一般的には純金融資産が1億円を超えると富裕層になります。資産運用で目標設定するうえで、重要な基準となるため覚えておきましょう。
金融資産に含まれる資産の種類

金融資産に含まれる資産の種類を以下にまとめました。
- 現金・銀行預金
- 株式
- 債券
- 投資信託
- 保険
- 商品券・小切手
- デリバティブ商品
- 仮想通貨
それぞれ詳しく見ていきましょう。
現金・銀行預金
現金または、銀行に預け入れをした預金は、金融資産のなかでも基本的かつ流動性の高い資産です。預金の場合は、普通預金・定期預金を利用することで一定の金利を得られることが特徴です。
そのまま支払いに使用できることから、生活資金や予備資金として確保されます。ただし、インフレが発生すると金利が物価上昇に追い付かず、実質的な購買力が目減りする可能性があります。流動性は高いですが、現金の状態ではお金を増やすことができません。
株式
株式は企業が事業資金を調達するために発行する金融資産です。所有者はその企業のオーナーの一部となり、配当金・株主優待などを受け取る権利を獲得できます。
投資した企業の価値が高まれば、株価が上昇するため、売却すれば利益を得られます。資産を保有して得られるインカムゲインと売買によって得られるキャピタルゲインの両方を狙うことが可能です。
ただし、株価の下落や上場廃止により、資金を失うリスクがあります。新興企業を中心に株価の変動率が高い株式もあり、リスクの高い投資先に注意が必要です。
債券
債券は、国や企業などが資金を借りるために発行する有価証券です。発行体は投資家に対して満期時に額面を返済する義務を負います。借用書であるため、定期的に利息が支払われることで安定した収益を得られることが特徴です。
株式と比較すると流動性は高くありませんが、債券市場で売却できます。また、債券は発行体の破綻によるデフォルト(債務不履行)が発生すると、元本割れを起こすことも。デフォルトに陥った場合を除いて、元本を確保した状態で設定された金利に基づいて安定した収益を得られる金融資産です。
投資信託
投資信託は、多数の投資家から集めた資金を専門家(ファンドマネージャー)が運用します。株式、債券、不動産、金・原油などのコモディティなどに分散投資し、その成果を投資家へ還元する金融商品です。
個別に株や債券を購入するよりも、少額から複数の銘柄に分散して投資できることが大きなメリットです。運用期間中は信託報酬などのコストを支払う必要があります。
基準価額をもとに売買され、値上がりすれば売却益(キャピタルゲイン)を得られます。商品によっては分配金(インカムゲイン)が支払われます。
保険
生命保険をはじめとする保険商品には、保険料を貯蓄する機能を備えた貯蓄型保険があります。契約期間満了時には、返戻率にもとづく返戻金が支払われるため、払い込み済みの保険料以上の資金が返還される仕組みです。
保障機能によりリスクに備えつつ、長期的な資産形成も並行できる金融資産です。基本的に元本割れの危険性はありませんが、中途解約をしてしまうと解約返戻金が払い込み済みの保険料を下回る場合があります。
商品券・小切手
商品券や小切手も現金と同様に利用できる金融資産です。ただし、現金とは異なり、支払う場所や場面が限定されるため、流動性は低いでしょう。特定の商品券を金券ショップなどに持ち込んだ場合は、換金の手数料や商品券の流動性を理由に還元率は100%にはなりません。
設定された額面通りに使用したい場合は、指定された場所・場面と利用方法で使用します。有効期限が決められている場合もあるため、期限を過ぎると価値を失うリスクもあります。
デリバティブ商品
デリバティブ商品(金融派生商品)は、対象となる投資対象の価格変動に基づいて価値が決まる金融資産です。例えば、日経平均などの株価指数を対象とするデリバティブ取引には株価指数先物があります。ドル円などの為替変動を対象とするFXもデリバティブ取引の一種です。
デリバティブ商品では投資対象となる株式を受け渡しません。証拠金を払って取引を開始してから、取引によって動いた金銭のみが移動します。基本的には元手以上の取引をおこなうレバレッジ取引が前提になるため、ハイリスクな金融資産です。
仮想通貨
仮想通貨(暗号資産)は、ブロックチェーンと呼ばれる技術を基盤とした現金の代わりに使用できる場所もある電子的な通貨です。国や中央銀行の保証がありませんが、ハッキングなど外部からの攻撃に強い、分散して管理する仕組みを取っています。
新興の金融資産であることから安定性が低く、価格変動が大きくなります。法定通貨である現金だけでなく、株や債券などの伝統的な金融資産と比較して、価値が安定しないことも多いためリスクの高い資産です。
金融資産に含まれない実物資産の種類

一方で、金融資産に含まれない実物資産の種類は以下のとおりです。
- 不動産
- 貴金属(金・銀・プラチナなど)
- オルタナティブ資産(アンティークコイン・ウイスキーカスクなど)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産
不動産は、土地・建物などの実在する資産であり、実物資産のなかでも知名度の高い投資対象です。実物資産は共通してインフレに耐性があります。
不動産投資では、不動産を入居者に貸し出すことで賃料収入を得られます。保有すると毎月高いインカムゲインを期待可能です。
不動産は物価上昇にともない地価や賃料が上昇しやすく、金融資産と比べて安定したリターンを期待できることが特徴です。一方で、実物の不動産を取得するためにはコストがかかりやすく、金融資産と比較して流動性も低いことから売買に時間がかかります。
貴金属(金・銀・プラチナなど)
貴金属は、工業・宝飾などに需要を持つ希少性の高い実物資産です。具体的には、金・銀・プラチナが挙げられます。なかでも金は、世界の中央銀行が外貨準備として積極的に保有する代表的な資産です。
金は株式と同じ動きをしないことが多く、株式市場が弱い局面で買われやすい傾向があります。株式と組み合わせて保有すると、全体のリスク分散に役立ちます。資産全体の分散を考えるうえで重要な実物資産といえるでしょう。
オルタナティブ資産(アンティークコイン・ウイスキーカスクなど)
オルタナティブ資産は、株式・債券などの伝統的な金融資産以外の実物資産です。アンティークコインやウイスキーカスク(樽)、クラシックカー、絵画、時計など多岐にわたります。
オルタナティブ資産は、一般的に希少性の高さとコレクション性の高さから価値が形成されます。例えば、アンティークコインは発行枚数が限定されていることから高い希少性を持ち、人気のデザインはコレクターからの人気も高いため、大きなプレミア価値が付きやすいです。
クラシックカーも希少性と人気の高い車を購入して、値上がりした段階で売却する投資方法です。ほかにもウイスキーカスク(樽)は、樽に貯蔵された状態で熟成年数の増加により価値が上がる性質を持ちます。
オルタナティブ資産は、伝統的な金融資産とは異なる値動きが期待できます。資産全体のリスク分散に役立つ長期的な値上がりが期待できる投資先です。
金融資産の保有に関するデータ一覧

幅広い金融資産を保有するうえで、日本と海外の金融資産の保有割合の比較や、年代・年収別の金融資産の保有額が気になる方もいることでしょう。金融資産に関するデータをそれぞれ紹介していきます。
日本と海外の金融資産の保有割合の違い
日本・アメリカ・欧州(ユーロエリア)の金融資産の保有割合を以下にまとめました。
| 日本 | 米国 | 欧州 | |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | 50.9% | 11.7% | 34.1% |
| 債券 | 1.3% | 4.6% | 3.1% |
| 投資信託 | 5.4% | 12.8% | 10.6% |
| 株式 | 14.2% | 40.5% | 21.5% |
| 保険商品 | 24.6% | 27.7% | 28.7% |
| その他 | 3.6% | 2.7% | 2.0% |
金融資産のなかでも現金・預金の割合が50%を超えたのは日本のみであり、米国では10%程度になりました。債券・投資信託・株式の保有割合を比較しても、日本がもっとも少ない割合となっています。
米国・欧州の割合が必ずしも正しいとはいえません。しかし、諸外国に比べると、日本の金融資産の分散保有は進んでいないことがわかります。
金融資産の平均保有額【年代別】
年代別の各金融資産の平均保有額を以下にまとめました。
| 年代 | 現金・預金 | 株式 | 投資信託 | その他 | 総保有額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | 131万円 | 34万円 | 41万円 | 60万円 | 266万円 |
| 30代 | 419万円 | 204万円 | 93万円 | 158万円 | 874万円 |
| 40代 | 496万円 | 219万円 | 126万円 | 340万円 | 1,181万円 |
| 50代 | 705万円 | 387万円 | 151万円 | 530万円 | 1,773万円 |
| 60代 | 1,090万円 | 504万円 | 248万円 | 657万円 | 2,499万円 |
| 70代 | 954万円 | 450万円 | 202万円 | 556万円 | 2,162万円 |
年代が上がるほど金融資産の保有額が増加しています。30代以降は投資信託よりも株式を保有する傾向にありますが、20代では株式と投資信託の保有金額が逆転する結果が見られました。どの世代も現金・預金を総保有額の40%~50%程度の水準で保有しています。
金融資産の平均保有額【年収別】
年収別の平均保有額を以下にまとめました。
| 年収 | 現金・預金 | 株式 | 投資信託 | その他 | 総保有額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 532万円 | 157万円 | 112万円 | 262万円 | 1,063万円 |
| 300~500万円 | 607万円 | 295万円 | 165万円 | 361万円 | 1,428万円 |
| 500~700万円 | 698万円 | 349万円 | 145万円 | 425万円 | 1,617万円 |
| 750~1,000万円 | 867万円 | 377万円 | 198万円 | 624万円 | 2,066万円 |
| 1,000~1,200万円 | 1,072万円 | 553万円 | 257万円 | 795万円 | 2,677万円 |
| 1,200万円以上 | 1,851万円 | 1,306万円 | 369万円 | 1302万円 | 4,828万円 |
年収が高くなるほど総保有額に占める株式・投資信託の割合が増しています。年収が1,200万円を超えると現金・預金に近い金額で株式が保有されるようになります。ただし、投資信託の保有額は株式とは異なり、年収が高くなるほど爆発的に増加するものではありませんでした。
年代別・年収別に金融資産の保有額の平均をまとめました。海外には割合で劣りますが、日本でも多くの人々が現金・預金だけでなく、株式・投資信託などの金融資産を保有していることがわかります。現金・預金以外に金融資産を分散していない方は、株式・投資信託をはじめとする金融資産の分散保有を検討してみましょう。
金融資産に投資するうえで知っておきたいポイント

金融資産に投資するうえで知っておきたいポイントは以下の3つです。
- 現金以外の資産を分散して保有する
- 国内だけではなく海外資産にも目を向ける
- 金融資産とあわせて実物資産も保有する
それぞれ詳しく解説します。
現金以外の資産を分散して保有する
現金・預金のみに割合が集中していると、インフレ時には金利に物価上昇が追い付かず、価値が目減りしていく危険性があります。インフレへの備えとして、現金以外の金融資産を組み合わせて持つことが有効です。
現金・預金以外の金融資産は、市場動向によって元本割れのリスクがあります。それでも、インフレ率を上回る成長が期待できる金融資産を適切に分散すれば、長期的には資産の実質価値の維持に役立ちます。自身のリスク許容度に合わせて、配分を考えましょう。
国内だけではなく海外資産にも目を向ける
金融資産を分散するなら国内だけではなく、海外資産にも目を向けましょう。為替変動で円安が進行した場合は、世界的に円の購買力が下がります。通貨が日本円に集中すると資産全体で影響を受けてしまいます。一部をドルなどの外貨の金融資産に換えていればリスク分散ができるでしょう。
また、日本だけでなく、アメリカ・欧州・新興国など複数の地域に分散して投資すれば、特定の国の経済が不安定になった場合もリスクが偏ることがないでしょう。通貨分散・地域分散を意識して金融資産を保有することで、よりリスクの少ないポートフォリオを形成できます。
金融資産とあわせて実物資産も保有する
分散投資を意識するなら、金融資産に限った分散では不十分です。実物資産もあわせて保有すれば、有事の際にも強い資産形成を実現できます。株・債券・投資信託などの金融資産は共通して、リーマンショック、コロナショックなどの大暴落時に大きく値下がりしました。
実物資産は、金融市場が混乱するなかでも影響を受けにくいです。物価上昇にも強いことから、インフレ対策にも優秀な資産です。金融資産だけでなく、一定割合を実物資産に配分することで、ポートフォリオ全体の安定性が高まるでしょう。
まとめ
金融資産は、現金・預貯金以外にも数多く存在しており、適切に分散すれば安定した資産形成ができます。株・投資信託など伝統的な資産から、ハイリスクな資産も含まれるため、それぞれの特徴を理解して保有を検討しましょう。
資産運用における分散や具体的な投資対象に悩んでいる場合は、専門家に相談することをおすすめします。当社では、資産運用の総合的なアドバイスをおこない、個人ではアクセスが難しい魅力的な投資先を紹介できます。金融資産への投資を検討している方は当社にご相談ください。