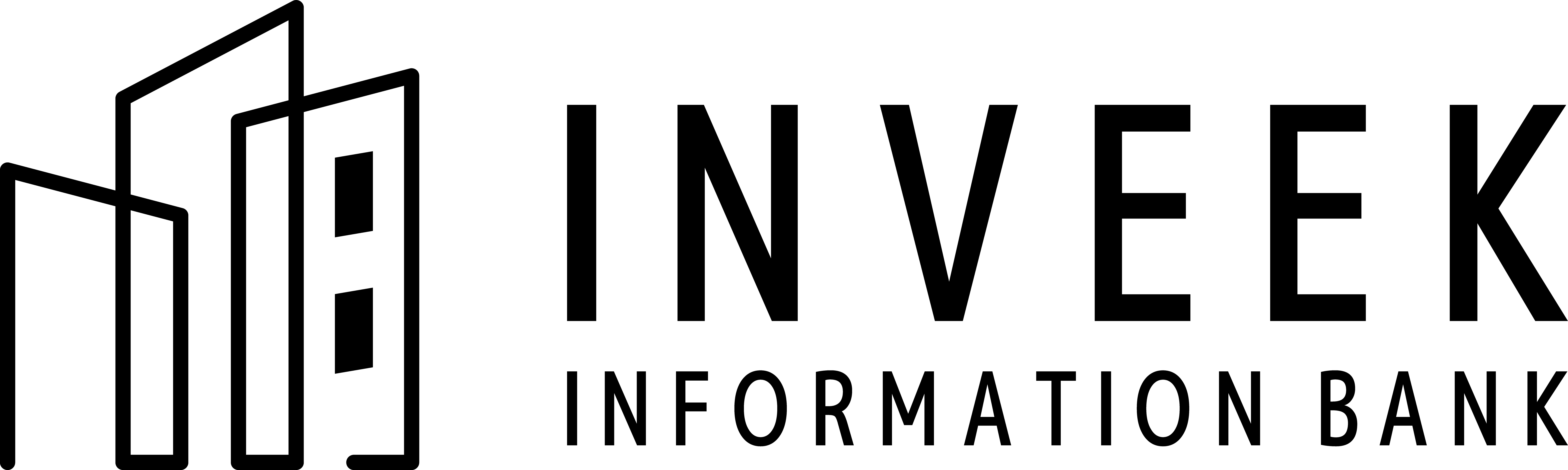公務員の方で、「資産運用を始めたいけれど、副業にあたるのでは?」と心配している方もいるかもしれません。
結論からいえば、公務員でも資産運用は可能です。原則として副業ができない公務員にとって、資産運用は本業以外の手段で収益を得られる貴重な手段といえるでしょう。
本記事では、公務員に資産運用がおすすめである理由と注意すべきポイントを解説します。公務員に適した具体的な投資も紹介するため、記事を読むことで公務員が資産運用を始めるために必要な情報を把握できるようになります。
公務員は副業禁止だが資産運用は可能

はじめに、公務員の副業は原則禁止されていますが、なぜ資産運用は可能なのか、その理由を順序立てて解説します。
公務員の副業は原則として禁止
公務員の副業は、国家公務員法第103条・104条で「営利を目的とする私企業の経営や役員就任」「報酬を得て事業への従事」を禁止されています。公務員の兼業を制限する規定であり、営利目的でない非営利団体と兼業する場合も許可制です。
副業を制限する主な理由は、公務の公正性・信頼性を担保し、税金を財源とする公務執行への影響を防止するためです。税金で給与を得る公務員が営利活動に熱心になれば、納税者からの信頼を損なう危険性があるでしょう。営利を目的として報酬を得る事業に、無許可で従事することは法律違反となります。
資産運用は副業ではない
国家公務員法で禁止されている副業とは、本業とは別に、継続的に収入を得るための「事業」や「労働」を指します。
一方、株式投資や投資信託などの資産運用は、あくまで個人の財産を管理する活動です。よって、副業禁止の規則に抵触しません。
しかし、アパートを何棟も経営するような事業規模でおこなう不動産投資は、規則に抵触する可能性があります。財産管理の一環と説明できる規模の資産運用であれば、副業禁止の規則に抵触することはないでしょう。
以上のことから、法律で公務員の資産運用は禁止されていません。事業活動に満たない規模であれば、勤務時間外に自由におこなえます。
公務員に資産運用がおすすめである理由

公務員の方に資産運用をおすすめする理由は、主に以下の2つです。
- 安定収入で資金を計画的に確保しやすい
- 金融機関からの信用が高い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
安定収入で資金を計画的に確保しやすい
公務員は給与水準が民間平均に合わせて決められます。リストラや倒産のリスクがほぼないため、長期間にわたって収入に大きな変動がなく働き続けられるでしょう。
安定した収入を得られることは、資産運用を始めるうえで有利になります。なぜなら、毎年・毎月の投資に回せる資金を計画的に算出しやすいからです。
予想外の収入減少により、資産運用の計画が崩れないことは強みになります。月々一定額を出資する積立投資を安定的におこなうことが可能であり、堅実に資産を増やせるでしょう。
金融機関からの信用が高い
公務員の社会的信用力は高く、金融機関からは安定した返済能力がある顧客とみなされます。金融機関によっては金利を優遇した公務員ローンを提供しており、公務員が一般的に優良な顧客として認識されている証拠です。公務員の信用力を活用すれば、資産運用でローンを利用した時に有利な条件で融資を受けやすくなります。
ローンを活用しておこなう代表的な資産運用は不動産投資です。公務員は金融機関から融資を受ける不動産投資を有利な条件で始めやすい立場にあります。このように、資産運用の種類によっては、公務員という立場が大きなアドバンテージになるでしょう。
公務員が資産運用をおこなう場合の注意点

公務員の方が資産運用をおこなう場合の注意点を5つ紹介します。
- 勤務時間中の取引は禁止される
- 業務と関連の深い企業への投資を避ける
- 不動産投資は事業規模によっては承認を得る必要がある
- 確定申告が必要になる場合がある
- 勤務先の副業規定を確認する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
勤務時間中の取引は禁止される
公務員は職務専念義務により、勤務時間中は本業以外の事務行為を一切おこなってはならないと定められています。よって、勤務時間中に投資をおこなうことは禁止されます。実際に公務員が勤務中にFX取引を数千回にわたっておこなったとして、職務専念義務違反で懲戒処分を受けた事例も。
公務員の資産運用が禁止されないケースは、勤務時間外で財産管理の私的行為にあたる場合です。勤務時間中に取引をおこなった場合はこの限りではなく、最悪の場合は処罰される可能性があります。
業務と関連の深い企業への投資を避ける
公務員は政策決定や行政監督などの業務を通じて未公開情報に触れやすい立場にあります。未公開情報をもとにした投資は、インサイダー取引に該当します。疑われないようにするためにも、担当業務と関わりの深い企業への投資は避けるようにしましょう。
金融商品取引法では、未公開情報を利用した株の売買は禁止されています。業務とは関係ない業界や地域の株、複数の株式に分散投資できる金融商品の投資信託に投資すれば疑われることはありません。
不動産投資は事業規模によっては承認を得る必要がある
公務員が不動産投資をおこなう場合、運用物件が増えると事業的規模に該当すると判断される可能性があります。具体的には、賃貸建物が5棟10室以上、家賃収入が500万円以上の場合は自営業として事業に該当します。
事業に該当するほど不動産投資の規模を拡大する場合は、事前に申請をおこない承認を得る必要があります。本業に支障をきたすことがないと判断されれば、事業規模を超える範囲であっても不動産投資の規模を拡大できます。また、相続などやむを得ない事情で規模を超える場合も事前に申請が必要です。
確定申告が必要になる場合がある
公務員の給与所得は年末調整がおこなわれるため、通常は確定申告が不要です。しかし、資産運用の収益が一定額を超えると確定申告が必要になる場合があります。
具体的には、投資利益が年間20万円を超えた場合は、雑所得として申告する必要があります。ただし、株や投資信託の取引口座を特定口座(源泉徴収あり)にしている場合や、個人投資家向けの税制優遇制度であるNISAを利用している場合は確定申告が不要です。
資産運用をおこなっていても必ず確定申告が必要になるわけではありません。しかし、必要なケースで申告を怠った場合は追徴課税のリスクがあるため注意が必要になります。
勤務先の副業規定を確認する
勤務先の省庁・自治体では、それぞれ地方公務員法・職員服務規程に基づく独自の副業規定が設けられています。資産運用は副業に該当しない場合が多いものの、部署によっては事前の届出や許可が必要なケースもあるため、副業規則を確認しましょう。
万が一、事前確認を怠り規約違反となった場合は、罰則の対象になる可能性があります。特に不動産投資をおこなう場合は、勤務先ごとの副業規定を確認してから始めるようにしましょう。
公務員におすすめの資産運用

ここでは、公務員の方におすすめの資産運用を5つ紹介します。
- 投資信託
- 不動産投資
- 生命保険
- 株式投資
- オルタナティブ投資(アンティークコイン、ウイスキーなど)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
投資信託
投資信託は、複数の投資家から集めた資金をまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式・債券・不動産などに投資・運用する金融商品です。
プロに運用を任せられるため、投資未経験の方でも安心して始められます。本業が忙しい公務員の方も資産運用に時間を取られることなく続けられるでしょう。複数の投資対象に分散投資できることから、リスクを軽減して安定したパフォーマンスを期待可能です。
少額から始めやすく、毎月一定額を積み立て続ける積立投資が有効です。公務員であれば、毎月安定した収入を期待できることから、投資資金を捻出しやすいでしょう。
日中の値動きを常に気にする必要がないため、規則に抵触する危険性はほとんどない金融商品です。気軽に投資を始めたい公務員の方にとっておすすめの資産運用になります。
不動産投資
不動産投資は、マンションやアパートなどの賃貸物件を購入し、家賃収入や売却益を得る投資手法です。公務員はローン審査の通過率が高く、金利優遇を受ければ低金利で賃貸物件の購入資金の融資を受けられます。
不動産投資の魅力は安定的な家賃収入(インカムゲイン)にあります。不動産の運用は管理会社に委託すれば、入居者の募集から日々の業務まで任せられるため、本業に支障をきたすことなく始められるでしょう。
事業規模に該当する場合は、事前に申請が必要になるため、場合によっては公務員の規則に抵触する可能性はあります。勤務先の副業規定も確認しながら、慎重におこなうようにしましょう。
生命保険
生命保険は、貯蓄型保険であれば保障と貯蓄性を兼ね揃えています。支払った保険料に一定の返戻率を掛けた金額が返還されるため、保険は資産運用の一部に組み込めます。
生命保険は資産運用の対象として見た場合、元本割れのリスクが低い安全資産です。生命保険料控除により、支払った保険料を申告すれば、所得控除で節税効果が期待できます。
万が一の場合は、保障を受けられるため遺族に対する備えにも最適です。公務員であれば投資信託と同様に事前に計画していれば、安定して毎月の保険料を支払えるでしょう。
生命保険は単独で高いリターンを獲得できるわけではありません。株や投資信託など、積極的にリターンを獲得する他の投資方法と組み合わせて利用します。全体のリスクを軽減され、より安定した資産運用が可能になるでしょう。
株式投資
株式投資は、企業の株を購入し、配当や株価上昇によるキャピタルゲインを狙う投資手法です。購入する株によっては、企業ごとにさまざまな特典が受けられる株主優待を得られます。
公務員は安定収入を背景に株を購入するためのまとまった資金を確保しやすいです。1単元(100株)の株を購入するために必要な資金は企業によっても異なりますが、安定して資金を用意しやすいでしょう。長期にわたって売却することなく、高配当・株主優待などのインカムゲインを安定的に得やすいことが魅力です。
ただし、平日の午前中から午後にかけて市場が開いていることから、勤務時間と重なり、取引をおこなうと処分を受ける危険性があります。公務員が業務で得た未公開情報を利用したインサイダー取引も禁止されているため、投資手法と投資先を吟味する必要があるでしょう。
オルタナティブ投資(アンティークコイン、ウイスキーなど)
オルタナティブ投資は、株や債券といった伝統的な資産とは異なる対象に投資する方法です。具体的な資産にはアンティークコインとウイスキーカスク(樽)があります。
アンティークコインは過去に発行され、発行枚数が限定された希少なコインです。世界中のコレクターの間で長期的に取引されており、継続して高い需要があります。
ウイスキーカスクは蒸溜したウイスキーを樽に詰めた状態で保有する新しい投資方法です。ウイスキーは樽のなかで熟成され、熟成年数を経るごとに価値を増す性質から長期的な価格上昇を見込めます。
長期間にわたって保有することで値上がりが期待できることから、長期投資と相性がいい実物資産です。
まとめ
公務員の資産運用は「事業」とみなされない範囲であれば、禁止されていません。むしろ、収入が安定している公務員は、将来を見据えた長期的な資産運用を計画的に進めやすい、という大きな強みを持っています。
資産運用を始めるにあたって不安なことや、「自分にはどんな方法が合っているのか知りたい」と感じたら、当社にご相談ください。お客様一人ひとりに合せて、資産運用の基本的なアドバイスから、具体的な投資商品の紹介まで、専門家が丁寧にサポートいたします。