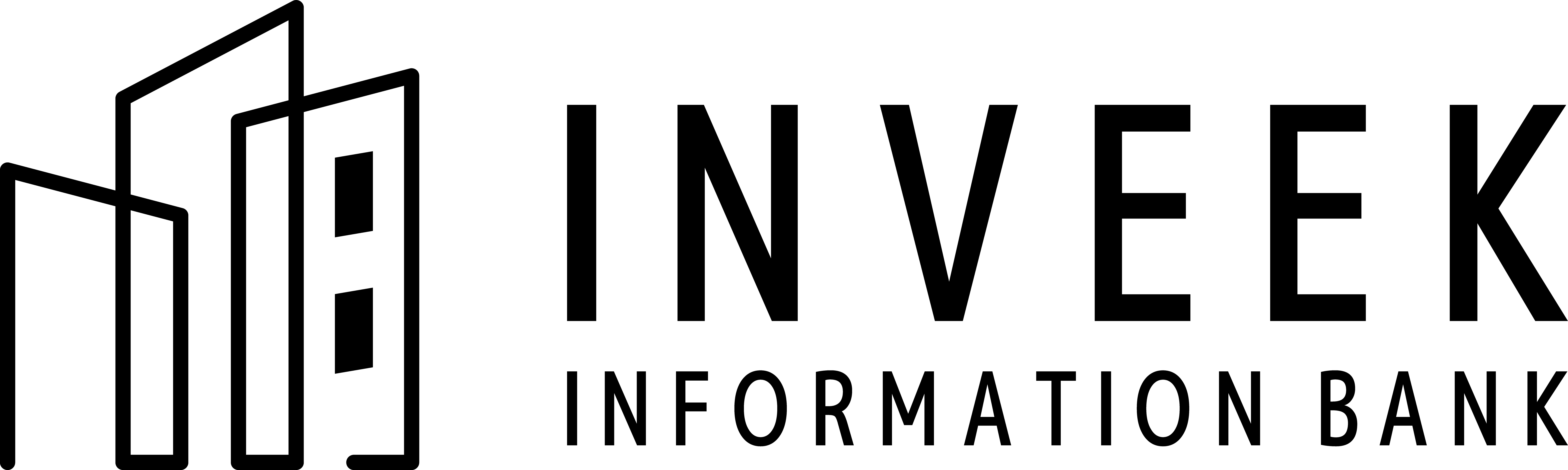NISA制度の拡充により、多くの人が投資をおこなうようになりました。なかでも投資信託は、少額から投資しやすいことから、投資初心者にも人気です。「投資信託を貯金の代わりにしよう」と考えて運用している方もいるかもしれません。しかし、投資信託には元本割れのリスクがあることから、すぐに使う可能性があるお金を貯める場合は、貯金の代わりにはできないでしょう。
本記事では、投資信託は貯金の代わりにならない理由と、投資信託と貯金を使い分ける考え方を解説します。記事を読むことで、貯金と並行しながら投資信託に適切に投資する方法がわかるようになります。
投資信託は貯金の代わりにならない理由

投資信託が貯金の代わりにならない理由は、以下のとおりです。
- 元本保証がない
- すぐに引き出しができない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
元本保証がない
投資信託が貯金の代わりにならない最大の理由は、元本保証がないことです。投資信託の価格は日々変動するため、購入時よりも価値が下がることがあり、元本割れが発生する可能性があります。
投資信託は、投資の専門家であるファンドマネージャーが運用しますが、運用成果が保証されるわけではありません。市場の動向次第では運用成績がマイナスになる可能性があり、結果として預けたお金が減るリスクを抱えています。
また、投資信託は運用を委託する手数料である信託報酬がかかります。信託報酬は、預けた資産から日々自動的に差し引かれる仕組みです。仮に投資を開始してから基準価額に変化がなかった場合でも、コストが発生し続ければ資産は目減りするでしょう。
資産が増える可能性もありますが、リターンがなければ基本的に預けたお金は減少します。額面を減らさずに資金を守る必要がある場合は、貯金の代わりにはならないでしょう。短期的な支出や緊急時に備える資金を預けるなら、預金のようにリスクを取らない場所でなければなりません。
すぐに引き出しができない
投資信託は預金と比較して、引き出しが不自由である点にも不安が残ります。投資信託は解約の手続きをしてから、実際に売却を完了して現金が口座に入金されるまでに時間がかかります。
証券会社から銀行口座への出金の反映にタイムラグがある場合は、さらに時間がかかることもあるでしょう。よって、急な出費があった場合に備えるためのお金の預け先としては適切ではありません。
投資信託は元本割れのリスクがあるため、引き出しが必要になるタイミングが損をしている時であれば、損失を確定させることになります。いざという時にお金が足りない場合は、損を承知で投資信託を解約せざるを得ない状況に陥るかもしれません。
また、投資信託によっては売却時にかかる手数料である信託財産留保額が設定されている場合があります。投資信託を解約して引き出してから再投資する場合、売買の回数が増えることになり、手数料がかさむ原因になることも。
必要な時に元本が減っている可能性があり、損をする不安を抱えるかもしれません。預金と比較してすぐにお金を引き出せないことがデメリットになります。生活費や緊急時に備える資金は、預金で安全に確保する必要があるため、投資信託を貯金代わりにはできないでしょう。
貯金だけではなく投資が必要である理由

投資信託は貯金の代わりにはなりませんが、貯金とは別に投資をおこなうことは重要です。貯金だけではなく投資が必要である理由を以下にまとめました。
- インフレに備えるため
- 預金ではお金を増やすことが難しい
- 将来は年金と貯金だけでは生活が難しくなる
それぞれ詳しく解説します。
インフレに備えるため
貯金だけでなく投資が必要とされる理由は、インフレに備えるためです。インフレとは、モノやサービスの価格が上昇する現象のことです。
物価が上がると、同じ金額で買えるものが少なくなるため、お金の実質的な価値が低下します。例えば、130円の缶ジュースが10年後に180円出さなければ買えなくなるとすれば、お金の購買力が低下したことになります。
インフレが進めば、現金をそのまま貯金しているだけでは、実質的にお金が減っている状態に陥るでしょう。日本は長らくデフレ傾向にありましたが、近年ではインフレが進んでいます。銀行にお金を預けているだけでは、物価上昇に追いつかず、実質的に資産が目減りしている状況です。
経済の仕組みから、インフレは一時的なものではなく、長期的に続くものと考えられています。老後資金をはじめ将来のために備えているお金は、今と同じ価値で使用できるとは限りません。よって、インフレを上回る成長を期待できる投資先で資産を運用する必要があります。
預金ではお金を増やすことが難しい
銀行預金ではお金を増やすことが難しいため、基本的に預金の役割は生活費や緊急時の資金など、すぐに使用する可能性があるお金の預け先になります。お金を増やす目的で預金にお金を預けることは、現状の日本の金利水準ではできません。
日本の金利は長年にわたって超低水準が続いています。インフレ率と比較して金利が負けているため、預金に預けると長期的には資産は減少すると考えられます。預金は短期的な資産の預け先としては安全ですが、長期ではインフレで実質的にお金を減らすリスクを抱えることになるでしょう。
投資はリスクを取る代わりにリターンを得ることが可能であり、投資信託に適切に投資をすれば安定して資産を増やすことができます。短期的な値動きを気にせず、長期的な成果を期待して投資を続けることが、インフレ率を上回る形でお金を増やすことにつながるでしょう。
将来は年金と貯金だけでは生活が難しくなる
老後を想定した時、将来的に受け取る年金と貯金だけでは生活が難しくなるかもしれません。日本は少子高齢化が急速に進んでおり、現役世代が減る一方で、年金を受け取る高齢者が増え続けています。
年金財政には大きな負担がかかっており、将来的には支給額の抑制や受給開始年齢の引き上げも考えられるでしょう。年金の不足分を補うために資産形成を進める必要があります。
年金の不足額を貯金で補う場合は、貯金を切り崩すことになり、途中で資金が尽きてしまうかもしれません。結果的に資金に不足がなかった場合も、貯金が目減りしていくことには不安がともない、老後の生活を送るうえで大きなストレスになることでしょう。
老後の資産形成では、投資によってお金に働いてもらう仕組みを作ることが重要です。年金の不足分を補える額のリターンが毎年発生するなら、貯金を切り崩すことなく生活できます。
将来に備えて適切に投資をおこなえば、働くことができない年齢になっても、お金に働いてもらうことで生活を安定させられるでしょう。
投資信託と貯金を使い分けるための考え方

投資と貯金はどちらか一方ではなく、目的に応じてバランスよく活用します。そのためには、「投資に回すお金」と「貯金として残すお金」を明確に区別する必要があるでしょう。投資信託と貯金を使い分けるための考え方は、以下のとおりです。
- 生活防衛資金は必ず貯金する
- 近い将来に必要な資金を確保する
- 余剰資金で投資信託に投資する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活防衛資金は必ず貯金する
貯金で優先して確保するべきお金は生活防衛資金です。生活防衛資金は、失業・病気・災害などの不測の事態が起きた時に、一定期間生活を維持するために必要なお金のことを指します。
生活防衛資金は、いつでも引き出せる状態で安全に保管しておく必要があるため、預金として持っておくことが望ましいでしょう。生活防衛資金の目安は、一般的に生活費の3カ月〜6カ月分になります。例えば、毎月の生活費が20万円であれば、60万円~120万円を確保する必要があります。
会社員の場合は上記で問題ありませんが、収入が不安定な自営業・フリーランスの場合は、1年分の生活費を目安に生活防衛資金を用意すると安心です。生活防衛資金を、元本保証がありすぐに引き出せる預金に預けておくことで、急な出費にも対応できます。
その結果、投資信託を売却しなくても資金を用意しやすくなるでしょう。
近い将来に必要な資金を確保する
次に、数年以内に使う予定のあるお金は、投資せず貯金として確保するようにします。使う時期が近い将来にあり、用途が明確なお金は投資に回すべきではありません。例えば、1年後に車を買うための資金を投資信託に回すと、市場の値動きによっては元本割れするリスクがあります。
必要な時期が決まっている資金はリスクを取らず、その時が来たタイミングで引き出せるようにしておきましょう。生活防衛資金とあわせて、使う予定が決まっているお金も預金としてキープしておきます。
余剰資金で投資信託に投資する
資産全体から生活防衛資金と、近い将来に必要な資金を差し引いて残ったお金が余剰資金です。余剰資金は、日々の生活に影響を与えない、当面使う予定がないと考えられるお金です。
余剰資金であれば、投資に回しても問題が起こりにくいことから、安心して運用できます。投資信託は長期にわたって運用を続けることで、安定したリターンを期待できます。しかし、数年以内に使用する可能性がある資金を投入すると、損失が出たタイミングで売ることになるかもしれません。
余剰資金であれば、一時的に損失が発生しても売却せずに保有を続けられます。使う予定がない資金であるからこそ、リターンが得られるまで待つことが可能です。
投資信託は、急な出費に備えるための貯金代わりにはなりません。しかし、生活防衛資金などを確保したうえで、毎月の収入の一部を投資信託に積み立てていく方法であれば問題ないと考えられます。
投資信託のリスクを軽減して続ける方法

投資信託を貯金代わりにできない理由は、元本割れの可能性があるため、一時的であっても総資産を減らしてしまうリスクがあるからです。よって、投資信託は貯金と使い分けることを前提に、無理なく継続できる態勢を整えることが重要になります。
投資信託のリスクを軽減して続ける方法を以下にまとめました。
- 長期を前提に始める
- ドルコスト平均法で投資する
- 複数の投資商品に分散する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
長期を前提に始める
投資信託のリスクを抑える基本的な姿勢は、長期投資を前提に始めることです。短期的な値動きのある投資信託は、日々の価格変動を気にしすぎると、相場が急落したタイミングで焦って売却し、損失を確定させてしまうかもしれません。
反対に利益が出たことを理由に、短期的に利益を確定させてしまえば、長期投資で得られたはずの利益を失う場合があり、機会損失につながります。投資信託は短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的に継続して投資を続けることが重要です。
投資信託(インデックスファンド)の代表的な投資対象である株価指数は、アメリカ全土の株式に連動する「S&P500」、アメリカのベンチャー企業向け株式市場であるNASDAQの時価総額上位100銘柄に連動する「NASDAQ100」、オルカン(オール・カントリー)の略称で知られる全世界の株式に連動する「MSCI ACWI」があります。これらの指数は短期的には上昇・下落を繰り返しますが、長期的には経済成長とともに右肩上がりの傾向を示しています。
過去のデータから投資信託は、保有期間が長くなるほど元本を下回るリスクは低くなります。よって、長期投資を前提に投資すれば、リスクの軽減が可能であり、大きなリターンを期待できるでしょう。具体的な期間は、10年以上を想定した保有が理想です。
ドルコスト平均法で投資する
投資信託のリスクを抑えるなら、まとまった資金を一括投資するのではなく、少額でも継続して投資する積立投資が効果的です。投資信託のリスクを抑える実践しやすい投資手法には、ドルコスト平均法があります。
ドルコスト平均法は、毎月一定の金額を継続的に投資し、価格が高い時は少なく、安い時は多く買うことで、購入単価を平均化する方法です。例えば、毎月1万円ずつ投資信託を購入する場合、値上がりして基準価額が高い月は少ない口数、反対に値下がりして基準価額が安い月は多い口数を購入します。
結果として、購入単価が平均化されます。購入のタイミングを読む必要がなく、価格変動のリスクを自動的に分散できることが強みです。
投資信託を購入する証券会社・銀行で自動積立を設定すれば、毎月の購入の手間をかけることなく、ドルコスト平均法による投資を自動化できます。感情に左右されることなく、投資を継続できる環境を整えられるため、リスクを抑えつつ長期で投資信託に投資する理想的な方法になります。
複数の投資商品に分散する
投資信託には数多くの種類があり、さまざまな投資対象に投資する商品が存在します。代表的な投資信託は株式に連動する株式型投資信託ですが、株式型投資信託のみに投資すると株式全体が暴落した場合に資産全体が影響を受けやすくなります。
投資信託を利用して複数の資産に分けて投資すれば、下落した資産をほかの資産で補うことが可能であり、全体のリスクをやわらげることが期待できるでしょう。株式以外の資産であれば、債券・不動産にも投資できます。株式とは逆相関にあるといわれ、株が下がれば価格が上がりやすい金(ゴールド)に投資できる投資信託もあります。
1本で株式・債券・不動産などに投資できるバランス型投資信託もあるため、投資信託への投資だけでも資産の分散は容易です。メインとなる株などの特定の資産の値動きに対して、リスクを軽減できるように資産を分散すると、より安定して投資を続けられるでしょう。
投資信託への投資で活用したい制度

投資信託に投資する場合、税制優遇の観点から活用したい制度があります。以下の2つの制度は共通して、投資信託にかかる税金を非課税にするメリットがある制度です。
- NISA
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
NISA
NISAは、個人投資家のための税制優遇制度であり、投資信託の運用益・分配金に課される税金が非課税になります。通常、投資信託の利益には20.315%の分離課税が課されますが、NISA口座で投資すれば税金はかかりません。
2024年から制度が改正され、非課税期間を定めることなく、無期限で課税されない投資が可能になりました。NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類の投資枠がありますが、投資信託への積立投資に適した投資枠はつみたて投資枠です。
つみたて投資枠では、年間投資上限額が120万円であり、毎月10万円までの積立投資ができる計算になります。NISA全体で最大1,800万円の投資額の投資信託を運用できる仕組みです。
投資信託はNISAを活用して投資すれば、税金の負担をかけることなく、効率的に資産を増やせるでしょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月一定の掛金を積み立て、投資信託などの投資商品を選んで運用し、老後の資金を準備するための制度です。NISAと同様に、投資信託の運用益が非課税になるだけでなく、複数の節税メリットを享受できます。
iDeCoの掛金はすべて所得控除の対象になるため、収入にかかる所得税・住民税が安くなります。また、年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除が適用される仕組みです。
掛金の上限は加入区分によって異なり、自営業者であれば毎月6万8,000円まで積み立てられますが、公務員の場合は2万円までしか積み立てられません。また、iDeCoには原則60歳まで引き出せない制約があるため、緊急時に利用する資金の預け先にはできません。
iDeCoを利用する場合は、投資信託を貯金代わりにした運用は不可能です。60歳まで引き出さないことを前提に投資を始めるようにしましょう。
投資信託以外で分散すべき投資先

投資信託だけでも投資方法次第では、一定のアセット分散はできます。しかし、よりリスクを軽減した最適なポートフォリオを形成するなら、投資信託以外の投資先にも目を向けるべきです。最後に、投資信託以外で分散すべき魅力的な投資先を紹介します。
- 貯蓄型保険
- 不動産投資
- オルタナティブ資産(ウイスキーカスク・アンティークコイン)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
6.1.貯蓄型保険
貯蓄型保険は、貯蓄・資産形成の機能を持つ保険商品であり、投資信託にはない保障機能を備えていることが魅力です。一定期間保険料を支払い、満期時に満期保険金を受け取ります。
満期保険金は一定の利率をかけて支払われるため、支払った保険料以上の資金が返還されます。元本が確保されているため、投資信託よりも安定した資産形成が可能であり、万が一の際には保障を受けられることがメリットです。
ただし、中途解約をした場合は、解約返戻金が支払った保険料を下回る元本割れが発生するリスクがあります。投資信託と並行しておこなう守りの資産形成として貯蓄型保険は有効な手段になるでしょう。
不動産投資
不動産投資は、物件を購入して家賃収入などの安定したインカムゲインを得ることを目的とした投資です。インフレに強い実物資産を保有し、長期的な安定収入が見込めます。
家賃収入は景気の変動に左右されにくく、入居者がいる限り毎月一定の収入が得られます。投資を始めてから収入が減少する老後に至るまで、本業以外で安定収入が期待できることは生活を考えるうえで心強いものになるでしょう。
投資信託でもREIT(不動産投資信託)、バランス型投資信託をとおして不動産に投資できます。しかし、不動産投資は、自己資金が少ない場合でも、ローンを利用して高額な賃料収入を期待できる物件を保有できることが魅力です。
ローンを利用できない不動産を投資対象にした投資信託では、高額なインカムゲインを得ることは困難です。実物資産の不動産は、株式・債券などの金融資産に投資する投資信託とあわせて保有すれば、よりポートフォリオの安定性が高められます。
オルタナティブ資産(ウイスキーカスク・アンティークコイン)
近年、注目を集めているオルタナティブ資産は、株式・債券などの伝統的な金融資産とは異なる投資対象です。そのなかでも、ウイスキーカスクやアンティークコインは世界中の富裕層から人気を集めています。
ウイスキーカスク投資は、ウイスキーが樽(カスク)熟成によって、時間とともに価値が上がる性質に着目した投資方法です。購入したウイスキーカスクを10年以上の長期にわたって保有すれば、熟成による価値の上昇による売却益が期待できます。
アンティークコインは、過去に発行された歴史的価値があるコインのことです。減ることはあっても増えることがない性質から高い希少性があり、世界中のコレクターから需要があります。実物資産であることからインフレに強く、長期的な保有で資産価値の大きな上昇が期待できるでしょう。
ウイスキーカスクやアンティークコインは、日本の証券会社で購入できる投資信託では投資対象にならないため、保有するには個別に投資する必要があります。長期的な資産形成に適した安定性の高い資産であるため、投資信託をはじめ伝統的な資産とともに保有すれば、より経済や市場の変化に強いポートフォリオを形成できるでしょう。
まとめ
投資信託は元本が保証されておらず、引き出しにも時間がかかるため、急な出費や生活費を確保する目的で貯金するなら預金しましょう。一方で、預金だけではインフレのリスクに備えられず、老後を含めた将来の生活に影響を与える可能性もあります。
そのため、生活防衛資金や近い将来に使うお金は貯金で守り、余剰資金を投資信託で運用する使い分けが重要です。投資信託を貯金の代わりにするのではなく、貯金と並行して長期的な資産形成の手段として活用することが、これからの時代では求められます。
当社では、適切なポートフォリオを形成するためのアドバイスから、投資信託以外で長期の資産形成におすすめの投資商品を紹介しています。最適な資産運用を実践したい方は、当社までお問い合わせください。