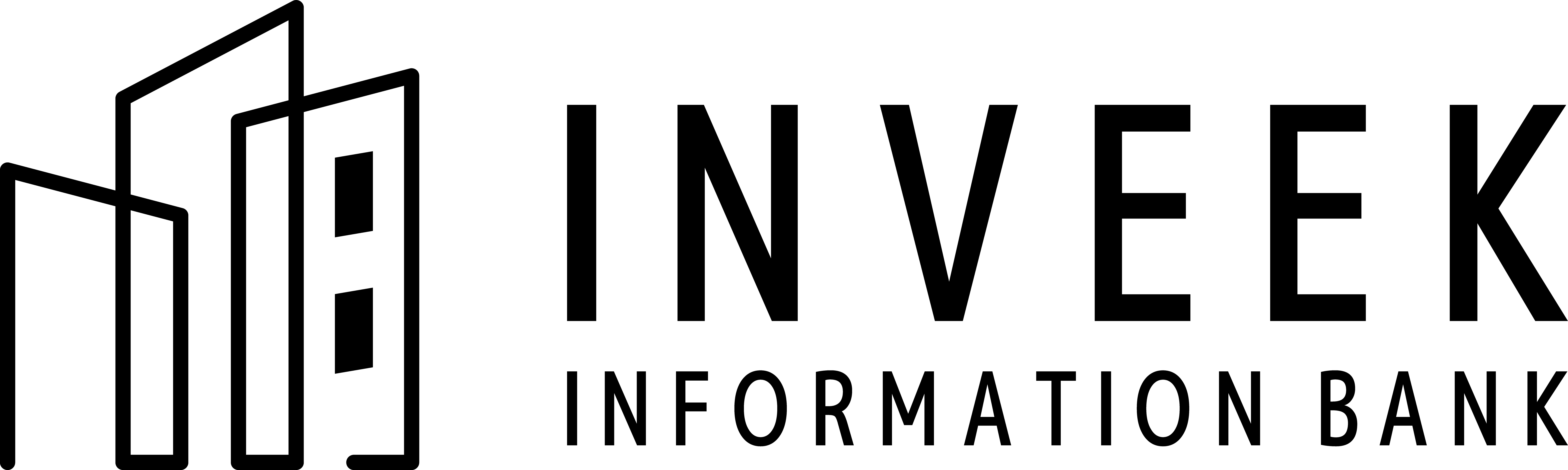「資産運用はやめとけ」という声を聞いて、本当に始めるべきか迷ったり、ためらったりしている方もいるかもしれません。結論からいえば、多くの人にとって資産運用は必要です。
ただし、投資に向き合う姿勢によっては、資産運用に失敗する可能性もあります。「失敗するリスクがあるならやらない方が良い」と考える人もいるでしょう。たしかに、資産運用に向いていない人には、いくつかの共通点があります。もしご自身に当てはまる点があり、それを改善できるのであれば、資産運用を始める前に見直しておくことが重要です。
本記事では、資産運用はやめとけと言われる理由と、資産運用に向いていない人の特徴を解説します。ネガティブな内容を踏まえたうえで、それでも多くの人にとって資産運用が必要である理由、気になるリスクを下げる方法、おすすめの資産運用を紹介します。記事を読むことで、自身にとって資産運用が必要であるかわかるようになるでしょう。
「資産運用はやめとけ」と言われる理由

日本では、資産運用や投資に対して、ネガティブな印象を持っている方は少なくありません。そのため、「資産運用はやめとけ」という考える人がいるのも、無理はないかもしれません。資産運用に対してマイナスな考えを持つ人がいる主な理由として、以下の3点が考えられます。
- 大損する可能性があるから
- 詐欺や悪徳業者が存在するから
- 手法によってはギャンブルと変わらないから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
大損する可能性があるから
資産運用では、銀行預金などとは違い、基本的に元本が保証されません。例えば株式の場合、その価値は株価によって決まり、日々変動しています。価格変動の幅は投資対象によって異なりますが、短期間で価値が大きく下落する可能性があります。
金融市場には、過去にリーマンショックやコロナショックのように、市場が大きく混乱する相場が訪れることがありました。このような市場が不安定な時期は、保有する資産によっては、価値が半減するほどの大損をするかもしれません。
実際に投資で大きな損失を出してしまった経験を持つ人からは「資産運用はやめとけ」という声が上がりやすいでしょう。また、そうした人の話を聞いて、資産運用に対してネガティブな印象を持ってしまう人もいると考えられます。
詐欺や悪徳業者が存在するから
日本に限らず、悪徳業者による投資詐欺の被害が後を絶ちません。金融庁から注意喚起もされていますが、「利益を出金できない」「突然連絡が取れなくなる」などのトラブルが多発しています。
代表的な手口は、高利回りを主張し、投資家から資金を集めても実際には運用をせず、新たに集めた資金を投資家に分配して詐欺を継続するポンジー・スキームです。運用実態がないことから、最終的には詐欺師が集めた資金を自分のものにして、連絡を絶つことで投資詐欺と発覚します。
詐欺によって失ったお金を法的に取り戻すことは難しく、たとえ訴訟を起こしても被害の回復は困難な場合が多いです。このような投資詐欺の存在が、「資産運用=危険」というイメージにつながってしまうことがあります。
手法によってはギャンブルと変わらないから
資産運用や投資に対して、FX(外国為替証拠金取引)のデイトレードのような、短期売買を連想する方もいるかもしれません。確かに、短期的な値動きだけを追いかけて頻繁に売買を繰り返し、その結果に一喜一憂するような投資スタイルはギャンブルに近いといえるでしょう。
他のギャンブルと同様に感情的に取引をするようになり、投資によってギャンブル依存症の状態に陥った例もあります。もちろん、これは一部の短期的な投資手法に見られる傾向です。しかし、こうしたイメージが先行し、「投資はギャンブルのようなものだ」と誤解して、資産運用全体を否定的に捉える人もいるのです。
資産運用に向いていない人の特徴

資産運用に向き合う姿勢によっては失敗する可能性もあります。失敗する可能性が高いことを理由に、資産運用に向いていない人の特徴を以下にまとめました。
- 今すぐに結果が出ないと満足できない
- 生活資金に余裕がない
- 一切のリスクを許容できない
上記のような考え方・状況に置かれている場合は、現状をあらためてから資産運用を検討したほうがいいかもしれません。それぞれ詳しく解説します。
今すぐに結果が出ないと満足できない
資産運用は長期を前提に利益を積み上げることで、最終的に大きなリターンを期待できます。短期間で大きく稼ぎたいと考えており、今すぐに結果が出ないと満足できない場合は、長期の資産運用は適していません。よって、ギャンブルと同じ構造になりやすいデイトレードなどの短期売買に手を出しやすくなります。
短期間で結果を求めるために売買を繰り返すと、取引コストが増加しやすく、期待どおりの継続的な利益を上げることは困難です。また、相場の値動きは常に予測不可能な要因に左右されることが、短期売買の難しさでもあります。
投資初心者が安易に手を出すと、十分なノウハウがないことから失敗しやすく、心理的にも負担が大きくなります。資産運用に対して短期的に結果が出せると考えている方は、認識をあらためましょう。
生活資金に余裕がない
投資は当面使う予定のない余裕資金でおこなうことが原則です。貯金がなく、明日の生活にも困っている状況では、投資に回せる余裕資金はないと言えるでしょう。資産運用は長期を前提におこなう必要がありますが、近い将来に必要になるお金で投資してしまうと、売却せざるを得ない状況になるでしょう。
また、資金の切迫に対する強迫観念が、短期的な利益確定をしてしまう原因にもなります。貯金がほとんどなくても、投資信託など少額から投資できる方法であれば始めることは可能です。しかし、生活に困るほど余裕がない場合は、資産運用の選択肢は狭くなるため、現在の状況を改善してから方法を考える必要があるでしょう。
一切のリスクを許容できない
多くの資産運用は共通して元本割れのリスクがあります。売却して利益を確定するタイミングではリターンが期待できる投資であっても、一時的に資産の評価額において損失が発生するかもしれません。一切のリスクを許容できない方にとって資産運用は難しいです。
元本割れのリスクを完全に回避しようとすると、現金保有を選ぶことになります。現金保有は額面における損失は発生しません。しかし、現金はインフレのリスクがあるため、持っているだけでもリスクに晒されています。インフレが進めば、将来的に今の貯金額で買えるものが少なくなるため、額面による損失はなくても、購買力の低下によって不利益を被る可能性があります。
そのため、多くの資産運用をする方は長期投資をおこなうことで、元本割れのリスクを許容しながらインフレのリスクに備えています。一切のリスクを許容できないことを理由に、資産運用にネガティブな印象を持っている場合は、現金のみを保有することで生じるリスクを認識するところから始めましょう。
多くの人にとって資産運用が必要である理由

ここまで資産運用のネガティブな印象や意見を中心に紹介しました。一部の人に適さない場合があることは事実ですが、それでも多くの人にとって資産運用は必要です。資産運用が必要である理由を以下にまとめました。
- インフレが進むと低金利の預金はリスクになるから
- 早く始めるほど複利で資産が増えやすいから
- 本業以外の収入の多様化につながるから
- 将来のライフイベントの備えになるから
- 老後のための資金を確保できるから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
インフレが進むと低金利の預金はリスクになるから
資産運用ではなく、定期預金で貯金をするほうがいいと考えている方もいるかもしれません。しかし、日本は長らく低金利環境が続いており、預金金利がインフレに追いついていない状況が続いています。
例えば、年2%のインフレが発生すれば、100万円の預金の実質的な購買力は98万円に減少します。一方で、定期預金の金利が0.2%の場合、利息は2,000円であるため、購買力が2万円減少するインフレ下では損をしているといえるでしょう。
よって、長期的にインフレが続くと予測される局面では、低金利の預金に預けることがリスクになります。インフレが預金金利を上回る状況で貯金を続けている方は、実質的に損をし続けている状態といえるでしょう。一定の貯金がある方は資産運用をおこなって、持っている現金をインフレから守る必要があります。
早く始めるほど複利で資産が増えやすいから
複利とは、資産運用で得た利息・分配金を元本に組み入れて再投資すれば、利息にも利息がつくことで効率的に資産を増やせる仕組みです。複利効果は長期的に運用するほど強力に働くため、若いうちであれば少額投資であっても、数十年以上の長期投資で大きなリターンを獲得できる場合があります。
例えば、年4%のリターンが期待できる投資対象に毎月1万円を積み立てると以下のリターンが得られます。
| 積立期間 | 投資元本 | 利益 | 資産合計 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 12万円 | 2,601円 | 12万2,601円 |
| 5年目 | 60万円 | 6万3,410円 | 66万3,410円 |
| 10年目 | 120万円 | 26万5,492円 | 146万5,492円 |
| 15年目 | 180万円 | 62万9,804円 | 242万9,804円 |
| 20年目 | 240万円 | 118万3,911円 | 358万3,911円 |
積立年数が増えるほど、複利効果により資産が効率的に増加していることがわかるでしょう。長期投資は早く始めるほうが有利になりやすいため、まとまった貯金がなく、少額投資しかできない方も今すぐに始める意味があります。
本業以外の収入の多様化につながるから
日本の実質賃金は30年前から上昇していない状態にあり、平均給与もほとんど変化がありません。会社員で本業の収入を増加させようとしても、現在の職種では収入が上がる余地がない方もいることでしょう。
転職による給与の上昇、副業による収入の増加を考えても、個人では働ける時間が限られているため限界があります。また、一つの収入源だけに頼っていると、病気やケガで働けなくなったり、会社の業績悪化や倒産、リストラなどで突然収入が途絶えてしまうリスクも。
資産運用を始めれば、労働以外の方法で収入を得られるようになります。運用期間中に分配金などのインカムゲインが発生する投資対象もあるため、本業以外で安定した収益が得られます。副業が禁止されている企業でも資産運用は認められることが一般的であるため、本業と並行して収入源を増やすことが可能です。
将来のライフイベントの備えになるから
結婚資金、住宅購入、子どもの教育費など、人生の節目となるライフイベントでは大きな支出が発生します。ライフイベントの支出は貯金だけで十分な額を賄うことは難しく、場合によっては必要なタイミングで資金が不足するかもしれません。
目標達成の時期にあわせて計画的に資産運用をおこなうことで、ライフイベントに対して効率的に資金を準備できます。結婚資金を5年後に用意する場合と10年後に住宅を購入する場合では、必要な資産運用も変わってきます。知識がない状態で目的に向けて効率的な運用をおこないたい場合は、資産運用の専門家に相談するといいでしょう。
老後のための資金を確保できるから
現状の日本の公的年金では、老後の生活費を賄うことが難しくなっています。そのため、年金だけではなく長期的な資産運用をおこなうことで、資金を確保する必要があるでしょう。
老後のための資産運用の考え方は、例えば、年金だけでは不足する老後の生活費が3,000万円であると仮定して、長い時間をかけて目標額を用意する方法が考えられます。ほかにも不動産投資の賃料収入など、年金以外にも継続して安定した収入が得られる資産運用を始めることで、老後の生活に備える方法もあるでしょう。
老後に不安がある方は、公的年金のみに依存しない生活費を確保するために、資産運用を早い段階から始めましょう。
資産運用のリスクを下げる方法

資産運用をやめとけと言われる背景には、さまざまなリスクの存在があることを解説してきました。投資にともなうリスクは完全には排除できませんが、適切な手法を考えることで大幅に軽減できます。資産運用をはじめるにあたって、リスクを抑える方法は3つあります。
- 少額から投資を始める
- 複数の投資先に分散させる
- 専門家の意見を聞く
それぞれ詳しく見ていきましょう。
少額から投資を始める
投資初心者の方が大損するリスクを抑えるためには、最初からまとまった資金を投入せず、少額から投資を始めることが重要です。仮に元本のすべてを失う可能性があるリスクの高い投資であっても、元本以上の損失が発生しないのであれば、投資額以上に損失が発生しないからです。少額投資であれば、元本自体が少ないことから、多額の損失は考えられません。
少額から設定した金額を毎月積み立て続ける定額投資は、少額投資であっても長期的に大きなリターンを期待できる投資方法です。また、少額投資をとおして資産運用に慣れることで、多額の資金を投資する場合も冷静な判断ができるようになります。まずは、リスクの少ない少額投資から始めましょう。
複数の投資先に分散させる
資産運用のリスクを下げるには、投資先を分散させることが非常に効果的です。複数の投資先に投資すれば、特定の資産が不調の場合もほかの資産が好調であればカバーできます。異なる資産を組み合わせることで、リターンを期待できる状態を維持しながら、リスクを軽減する効果が期待できるでしょう。
ただし、分散方法には注意が必要です。例えば、株式に投資する場合に複数の銘柄にのみ分散して投資することは狭い意味での分散であり、株式市場全体が急落すればすべての資産がリスクに晒されます。株式や債券などの有価証券、不動産や金などの実物資産、貯蓄型の生命保険などの低リスク資産など、それぞれ異なる種類の資産への分散投資が重要です。
同じ有価証券に投資して銘柄を分散させることはポートフォリオ分散、複数の異なる種類の資産への分散はアセットアロケーション分散と呼んでいます。投資先の分散はポートフォリオだけではなく、アセットアロケーションの視点で考えるようにしましょう。
専門家の意見を聞く
投資初心者の方は資産運用の勉強から始める必要があります。しかし、独学で勉強するなかで誤った知識にとらわれてしまうと、リスクの高い投資方法を選んでしまう場合や、投資詐欺の被害に遭うかもしれません。リスクを避けながら効率的に資産運用を学ぶには専門家の意見を聞くことがおすすめです。
投資の知識がない場合も専門家がわかりやすく解説してくれるため、資産運用に対する理解が深まりやすいです。相談する専門家は銀行・証券会社などの金融機関に所属する人ではなく、中立的なアドバイスを受けられるファイナンシャルプランナー(FP)、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)を選びましょう。
特定の投資商品を勧めるのではなく、ご自身の資産状況を踏まえたうえで適切な資産運用の選び方をアドバイスしてもらうためには、大手金融機関に属さない独立した立場にある専門家が適しています。
分散投資に最適なおすすめの資産運用

アセットアロケーション分散を考えるにあたっては、資産運用を広く知ることが重要です。分散投資をするうえで、有力な候補となるおすすめの資産運用を5つ紹介します。
- 投資信託
- 不動産投資
- 生命保険
- ヘッジファンド
- オルタナティブ投資(金、アンティークコイン、ウイスキーなど)
それぞれ詳しく解説します。
投資信託
投資信託は少額から幅広い資産に分散できる商品であり、株式や債券などの有価証券を中心に、不動産や金などの実物資産にも投資できます。一つの商品を購入するだけでポートフォリオ分散がしやすく、商品の種類や複数の商品を組み合わせることでアセットアロケーション分散もできます。
投資信託の価値を示す基準価額が設定されており、基準価額の上下によって損益が決定する仕組みです。種類にもよりますが価格の変動が1日1回であるため、短期よりも長期投資に適した商品です。
NISA・iDeCoなどの制度を活用すれば、投資の利益を非課税にできるため、税金の節約も可能です。証券会社の口座を開設すれば、商品によっては100円から投資できるため、資産運用が初めての方も投資しやすいでしょう。
不動産投資
不動産投資は、賃料という安定した収入を生むだけでなく、物件によっては長期的な価格上昇が期待できるため、インフレ対策にもなります。物件の購入が必要であるため、ローンを含めて投資額は高額になりやすいです。
法によっては、不動産投資でも複数の物件に投資するポートフォリオ分散が可能です。不動産は、株や債券などの有価証券と並ぶ代表的な投資先になっています。
生命保険
貯蓄型の生命保険は、万が一の保障と資産運用の2種類の性質をあわせ持つ優秀な商品です。死亡保障が生涯続く終身保険、子どもの教育準備資金を確保する学資保険など、目的にあわせて加入できます。
満期時や解約時には、支払った保険料に対して一定の利率を乗じた保険金が支払われます。支払った保険料は生命保険料控除を受けられるため、節税効果も期待可能です。保障と両立して目的にあわせた安定した資産運用ができることでしょう。
ヘッジファンド
ヘッジファンドは、証券会社で購入できる一般的な投資信託と比較して、多様な投資戦略を駆使して投資する限られた人に販売する投資商品です。例えば、相場が下落している局面では、売りから取引に入る空売り(ショート)をおこなうことで市場環境に依存せずに利益を追求できます。
ヘッジファンドは個人投資家ではなく、機関投資家向けに販売されることも多いです。購入できる機会が限られており、投資額も高額になりやすいことから、個人投資家の投資が難しいケースもあります。
しかし、専門家によっては紹介する資産運用にヘッジファンドを含める場合もあるため、効率的な資産運用を考えるうえで有力な選択肢といえるでしょう。当社では、個人の方も投資可能な非常に優秀な運用成果を上げているヘッジファンドを紹介できます。ヘッジファンドに興味があっても、どのように投資すればいいのかわからない方はご相談ください。
オルタナティブ投資(金、アンティークコイン、ウイスキーなど)
オルタナティブ投資は、株式や債券といった伝統的な資産(有価証券)とは、相関性の低い値動きをする資産に投資します。有価証券を対象にする投資信託に投資する場合、アセットアロケーション分散を考えるにあたって非常に重要な資産といえるでしょう。
オルタナティブ投資の代表例としては、まず金(ゴールド)が挙げられます。金は、株式とは異なる値動きをする資産として知られており、インフレの進行や経済的な不安が広がる局面で値上がりします。
しかし、近年では新しいオルタナティブ投資も注目されています。例えば、アンティークコインもその一つ。これは、古くに発行された希少性の高いコインです。世界中のコインコレクターの間で取引されており、高いプレミア価値がついています。減ることはあっても増えることはない性質から、年々希少性が高まるため、市場において長期的な価格の上昇が期待できるでしょう。
また、ウイスキーへの投資も注目されています。この場合、ボトル詰めされた状態ではなく、熟成期間中の樽(カスク)を所有する方法が一般的です。ウイスキーは樽のなかで熟成するお酒であり、熟成年数を重ねるほど価値が高まります。熟成していない状態で購入したウイスキーを長い時間をかけて熟成させれば、大幅な価値の上昇が期待できるでしょう。
オルタナティブ投資は、代表的な金だけではなく、アンティークコインやウイスキーといった、個人の趣味や関心と結びつきやすい対象に投資できることが魅力です。
まとめ
「資産運用はやめとけ」といった声には、さまざまなリスクが背景にあります。しかし、資産運用は正しい知識と姿勢を持って取り組めば、将来の不安を軽減する有効な手段です。
インフレや公的年金の将来への懸念といった社会の変化を考えると、リスクがあっても資産運用は多くの方にとって積極的に取り組むべきものといえるでしょう。資産運用にともなうリスクは、少額から始める、分散投資を心がけるなどの対策によって、大きく軽減できます。
リスクをまったく取らないのではなく、リスクをできる限り回避しながら、リターンを高める考え方がこれからの時代には必要です。投資初心者で不安がある場合は、中立の立場から助言を受けられる専門家に相談して、自分にとって適切な方法で資産運用をおこなうようにしましょう。