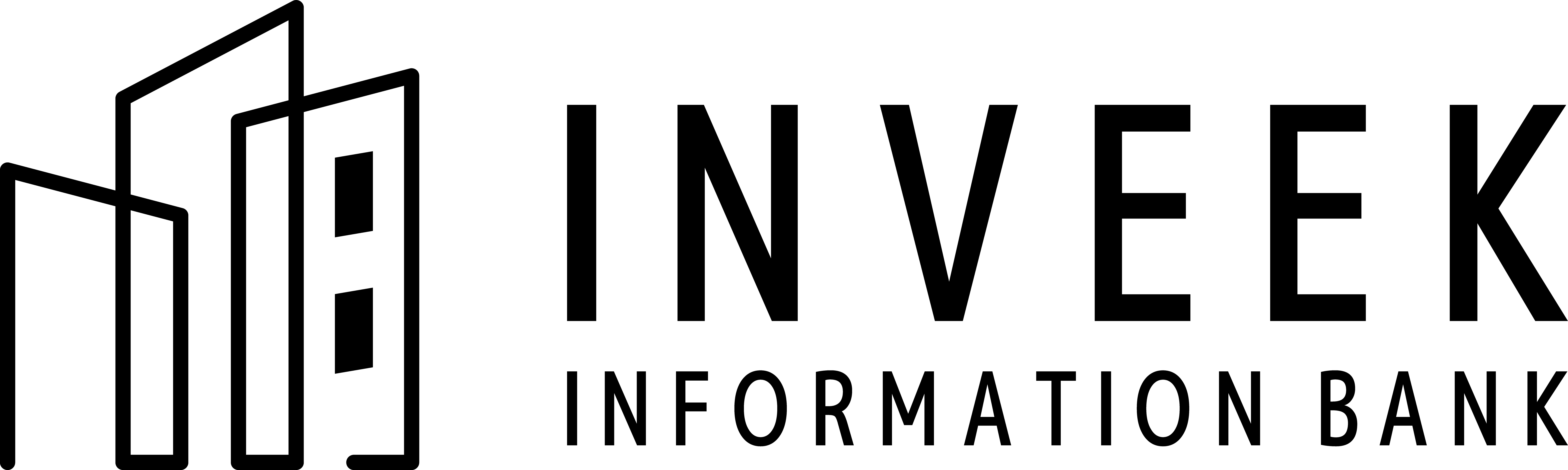サラリーマンとして働いていても収入が増えない悩みを持っており、お金を増やす手段として投資や資産運用に興味があるものの、知識がないために一歩を踏み出せない方もいるのではないでしょうか。投資初心者も実践しやすい資産運用をおこなうことで、今ある貯金を増やすことが可能です。
数年前よりも生活が苦しくなった実感があり、将来に不安を覚えている方にこそ資産運用は必要です。サラリーマンの資産運用では、本業の妨げにならず、両立できる投資を選ぶことが重要になります。
本記事では、サラリーマンにも資産運用が必要である理由と投資初心者で資産運用を選ぶポイントを解説し、具体的なおすすめの資産運用を紹介します。記事を読むことで、投資初心者かつサラリーマンで資産運用を始めるために必要なことがわかるようになるでしょう。
サラリーマンにも資産運用が必要である理由

サラリーマンにも資産運用が必要である理由を以下にまとめました。
- 長期にわたって給与が上昇していないから
- 税金・社会保険料の潜在的な負担が増加しているから
- 金利が低く貯金だけでは資産を増やすことが難しいから
- 物価上昇が続いておりインフレに備える必要があるから
- 年金だけでは老後資金に不安があるから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
長期にわたって給与が上昇していないから
サラリーマンは、経営者や自営業者と違い、個人の働きによって給与収入が大きく増加する余地がない立場にあります。よって、昇給は所属している会社に依存するでしょう。また、日本のサラリーマンの給与は、長期にわたって上昇していないのが現状です。根拠となる実質賃金と平均給与のデータを以下にまとめました。
実質賃金の伸び率(1995年~2020年)

| 国 | 実質賃金の伸び率 |
|---|---|
| スウェーデン | 2.2% |
| ノルウェー | 2.1% |
| フィンランド | 1.7% |
| イギリス | 1.7% |
| アメリカ | 1.4% |
| デンマーク | 1.4% |
| フランス | 1.1% |
| ドイツ | 0.9% |
| オランダ | 0.7% |
| イタリア | 0.5% |
| 日本 | 0.0% |
平均給与
| 年度 | 平均給与 |
|---|---|
| 2014年 | 421万円 |
| 2015年 | 423万円 |
| 2016年 | 425万円 |
| 2017年 | 434万円 |
| 2018年 | 439万円 |
| 2019年 | 438万円 |
| 2020年 | 435万円 |
| 2021年 | 446万円 |
| 2022年 | 458万円 |
| 2023年 | 460万円 |
他国と比較した1995年~2020年の実質賃金の伸び率は、アメリカ・イギリスなどの先進国で1%を超えており、国によっては2%を超えています。しかし、日本の伸び率は0%であり、他国と比較して低迷しているといえるでしょう。2014年から2023年までの10年間における平均給与もほとんど変化していません。
以上のデータから、サラリーマンの給与は上昇していないものの大きく減少もしていないことから、安定した収入を得やすいことがわかります。しかし、給与の大きな上昇を期待できる状態にはないことから、サラリーマンを続けて現在よりも多くのお金を得るためには、本業以外の方法を考える必要があるでしょう。
税金・社会保険料の潜在的な負担が増加しているから
給与が変わっていなくても、生活が苦しく感じる大きな理由には、税金・社会保険料など潜在的な負担が増加していることが挙げられます。サラリーマンの給与からは、所得税・住民税などの税金、健康保険・厚生年金保険などの社会保険料が差し引かれます。
所得に占める税金・社会保険料の負担は、国民負担率という指標で計ることができます。平均給与・実質賃金が伸びないなかで、国民負担率は以下のように推移してきました。
国民負担率
| 年度 | 国民負担率 |
|---|---|
| 2014年 | 42.4% |
| 2015年 | 42.3% |
| 2016年 | 42.7% |
| 2017年 | 43.3% |
| 2018年 | 44.2% |
| 2019年 | 44.2% |
| 2020年 | 47.7% |
| 2021年 | 48.1% |
| 2022年 | 48.4% |
| 2023年 | 46.1% |
10年にわたって給与が変わっていないにもかかわらず、国民負担率は上昇傾向にあります。1995年まで遡れば国民負担率は35.7%でした。収入は伸びなくても税金・社会保険料の負担が重くなることから、年度を重ねるにつれてサラリーマンで生活の苦しさを実感する人が増えています。
物価上昇が続いておりインフレに備える必要があるから
生活が苦しいと感じる理由は、税金・社会保険料だけでなく、インフレも大きな理由の一つです。サラリーマンの給与が変化していないということは、物を購入するための購買力が上がっていないことを示しています。
購買力が上がっていない状態で、物価の上昇によりインフレが発生すれば、生活費も高騰するため生活が苦しくなるでしょう。物価の上昇やインフレを判断する指標には、消費者物価指数があります。以下に消費者物価指数の推移をまとめました。
消費者物価指数(2020年を100とする場合)
| 年度 | 消費者物価指数 |
|---|---|
| 2014年 | 98.0 |
| 2015年 | 98.2 |
| 2016年 | 98.2 |
| 2017年 | 98.9 |
| 2018年 | 99.6 |
| 2019年 | 100.1 |
| 2020年 | 100.0 |
| 2021年 | 103.2 |
| 2022年 | 106.3 |
| 2023年 | 109.5 |
消費者物価指数は、2014年から+1.0以下の緩やかな上昇傾向にありましたが、2020年以降は+3.0に近い大きな上昇を続けています。数値が大きく上昇した年度では、物価上昇に対する実感がある人も多いことでしょう。
今後も消費者物価指数は上昇する可能性が高いことから、物価上昇に備える必要があります。現在は100円で購入できるものも、インフレが進めば150円を出さなければ購入できなくなるからです。つまり、貯金しているお金の価値もインフレが進めば減少します。
資産運用はインフレから現在持っているお金を守る役割も持ちます。また、貯金ではなく資産運用が推奨される理由はインフレだけではありません。
金利が低く貯金だけでは資産を増やすことが難しいから
1990年代まで日本は定期預金において高金利を維持してきました。しかし、1990年代後半になると金利は大きく下落し、低金利の時代が続いています。例えば、定期預金で6%の金利がつく高金利の時代と、0.2%の低金利の時代を比較してみましょう。
6%の金利では1,000万円を預けると年間で60万円の利息がつきますが、0.2%の金利では2万円の利息しかつきません。金利の低い時代では、貯金をしてお金を預けるだけでは資産を増やすことが難しいです。
よって、生活に必要なお金や近い将来に支出するお金を除いて、預けるだけでなく、資産運用で積極的に増やすほうが効率のいい時代であるといえます。
年金だけでは老後資金に不安があるから
かつて金融庁が発表した高齢夫婦の無職世帯が年金で生活していくには2,000万円が不足するという発言が話題となり、老後の資産形成を考えるうえで、老後2,000万円問題が知られるようになりました。
2,000万円は平均値であるため、すべてのサラリーマンが老後に年金で暮らすうえで必ずしも2,000万円が必要になるとは限りません。2,000万円以下でも十分となるケースもあれば、反対に2,000万円では不足するケースも考えられます。
しかし、老後2,000万円問題から、サラリーマンが一般的に受け取る厚生年金だけでは、老後を生活するのは難しいことがわかるはずです。年金だけでは老後資金に不安があるため、老後の資産形成を前提に資産運用をおこなっていくことがこれからのサラリーマンにとって重要になります。
投資初心者のサラリーマンが資産運用を選ぶ際のポイント
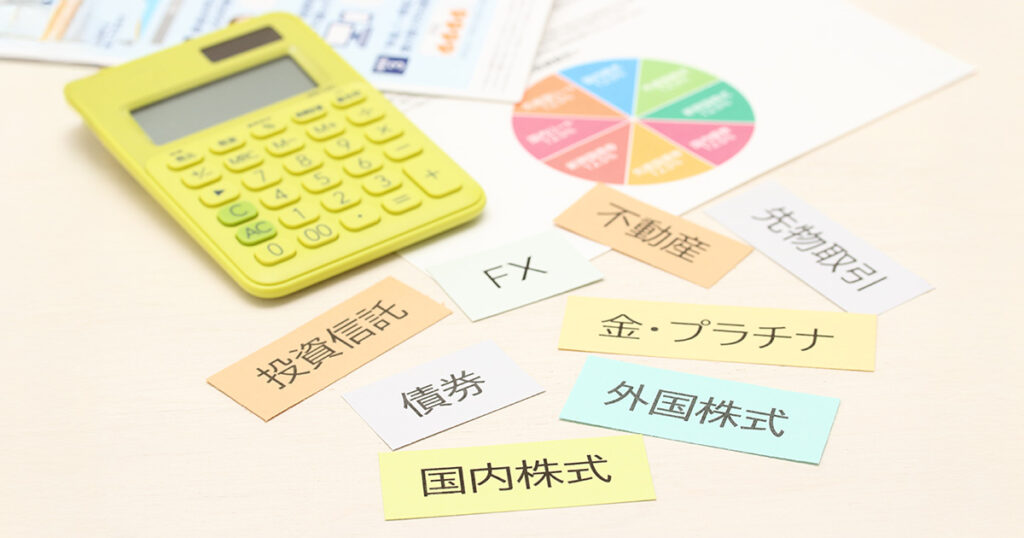
投資初心者のサラリーマンの方が資産運用を始める際に、特に押さえておきたいポイントは4つあります。
- 長期にわたって安定した投資ができる
- 値動きを頻繁に確認しなくても問題がない
- NISA・iDeCoなどの節税制度を活用できる
- 安定収入と企業与信で銀行融資を活用できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
長期にわたって安定した投資ができる
サラリーマンは給与収入が安定しているため、余剰資金を継続的に積み立てやすいです。長期投資の基本である、毎月決まった金額を積み立てる定額投資を実践しやすいでしょう。定額投資の優れている点は、投資対象の価格変動のリスクを最小限に抑えられることです。
例えば、投資を始めた月に投資対象が下落しても、次の月に購入すれば購入単価が減少します。積み立てる回数が増加するほど、購入単価が平均化されるため、誰が実践しても同じ結果を出しやすくなります。
よって、投資初心者のサラリーマンの方にとって長期にわたって安定した投資ができる定額投資は適した方法といえるでしょう。
値動きを頻繁に確認しなくても問題がない
サラリーマンは平日の日中は本業に集中する必要があるため取引ができません。そのため、値動きを頻繁に確認しなくても問題がない投資対象、投資方法を選ぶ必要があります。よって、日中も値動きがある投資対象に短期的に投資することは推奨できません。
値動きの確認が少なくても問題がない投資方法は長期投資であり、投資対象によっては年1~2回程度確認するだけでも支障はないでしょう。値動きを確認しなくても問題がない投資対象の特徴は、資産運用のプロや専門家に運用をすべて委託できる投資方法です。
忙しいサラリーマンであっても、資産運用に時間を取られることはなく、本業に専念できます。
NISA・iDeCoなどの節税制度を活用できる
資産運用をおこなうなら、お金を増やすだけでなく、節税などの負担を軽減する方法をあわせて検討しましょう。NISAを利用すると株式や投資信託にかかる税金が非課税になります。株式・投資信託の利益には通常20.315%の税金がかかるため、効率的に資産を増やせる制度といえるでしょう。
また、安定した収入を得ているサラリーマンにとって、資産運用で年金を作る制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金)は投資の利益が非課税になるだけでなく、掛金の全額が所得控除の対象となることが魅力的です。本業の収入に対して所得税・住民税の節税効果を期待できます。
活用できる節税制度を利用して、税金の負担軽減を含めてサラリーマンにとって効率的な資産運用を目指していきましょう。
安定収入と企業与信で銀行融資を活用できる
社会的な信用がある企業に務めるサラリーマンが資産運用を始める場合、安定収入と企業からの信用(企業与信)を活用できることは、大きなアドバンテージです。具体的には、不動産投資で銀行融資を受ける場合に有利になります。
銀行は安定した給与収入を持つサラリーマンに対しては融資をおこないやすく、有利な条件で不動産投資ローンを組みやすくなるでしょう。不動産投資は、本業の収入以外の第二の収入源を築けるメリットがある投資であるため、安定した収益を得られます。
また、不動産投資では、投資物件の購入費用を耐用年数に応じて毎年の経費として計上できる減価償却を利用可能です。実際の支出を伴わない赤字が発生するため、利益に課税される所得が減少します。
サラリーマンの方にとって特に注目したいのが、損益通算という制度です。減価償却によって不動産所得が赤字となった場合は、その赤字分を本業の給与所得から差し引くことができます。損益通算により、本業で得た課税対象となる所得が減少し、所得税や住民税の負担軽減が可能です。
ほかにも、不動産投資ローンを組むにあたって団体信用生命保険(団信)に加入できることもメリットです。団信はローン契約者が死亡または高度障害状態になった際に、残債が保険で完済される仕組みです。自身に万が一があった場合も、家族に資産としての不動産が残されることになります。
社会的な信用が高く、安定した収入を持つサラリーマンの方は、不動産投資など融資を受ける資産運用において有利になるでしょう。
サラリーマンにおすすめの資産運用

サラリーマンの方におすすめの資産運用は以下のとおりです。
- 投資信託
- 株式投資
- 不動産投資
- 生命保険
- オルタナティブ投資(アンティークコイン・ウイスキーなど)
それぞれ詳しく解説します。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金を資産運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などに分散投資します。運用成果は定期的に支払われる分配金や、売却時に売却益として受け取る金融商品です。
商品によっては100円程度から始められる少額投資が可能であり、忙しいサラリーマンでも証券会社のサービスを利用して自動積立ができます。一つの商品に投資するだけで自動的に分散投資されるため、投資対象を自分で選ぶ必要がありません。
投資信託には不動産を投資対象とするREIT(不動産投資信託)もあります。実際に物件を購入しなくても不動産に少額から投資できる方法です。投資信託は株や債券以外にも、金などのコモディティに投資できる商品もあるため、幅広い投資対象に気軽に投資できるメリットがあります。
NISA・iDeCoなど節税制度の対象となっていることから、税金の負担を減らしやすい投資先でもあります。投資額・投資方法を含めて気軽に始めやすい資産運用といえるでしょう。
株式投資
株式投資は、企業が発行する株式を売買して、売却益や配当金を得る投資方法です。投資信託とは異なり、個別に銘柄を選定する必要があるため、手間がかかるかもしれません。しかし、個別銘柄ではさまざまな恩恵を受けられる株主優待を獲得できるため、投資信託にはないメリットがあります。
株式市場が開場するのは平日の日中であるため、サラリーマンの働いている時間と重なります。しかし、日々の値動きに左右されない長期を前提とした投資方法を選択するか、証券会社が提供している夜間取引を利用すればサラリーマンも株式に投資可能です。
投資信託と同様にNISAの対象となっているため、税金の負担を軽減できるでしょう。ただし、自己判断が求められる部分が大きいことから、投資初心者の方は方針を明確にしたうえでおこなうようにしましょう。
不動産投資
不動産投資は、物件を利用して賃料収入、または売却益を得る投資方法です。サラリーマンに適している理由は、安定した収入が物件の融資審査において有利に働きやすいからです。金融機関から融資を受けることで、自己資金では購入できない高額で高い利回りを期待できる物件を購入できます。
物件を購入して運用する不動産投資は、住人の募集などの実際の運用は不動産管理会社に委託できます。しかし、成功をするには法律を含めた不動産に関する勉強が必要です。
生命保険
貯蓄性のある生命保険は、万が一の保障と資産運用を同時に実現できる金融商品です。保険料は掛け捨て型より高額ですが、満期時には運用利率を含めた保険金が支払われます。
また、貯蓄型の生命保険には種類があり、目的に合わせて保障と貯蓄方法を選ぶことが可能です。以下に種類と内容をまとめました。
| 保険の種類 | 内容 |
|---|---|
| 終身保険 | 一生涯の死亡保障があり、保険料払込期間終了後も保障が続く |
| 養老保険 | 一定期間の保障と満期時の保険金がある |
| 個人年金保険 | 所定の年齢から年金形式で保険金を受け取れる |
| 学資保険 | 子どもの教育資金を計画的に準備、死亡保障がある |
上記のとおり生命保険は種類によって特徴があるため、目的に合わせた資産形成と保障を並行しておこなえます。また、掛金を申告すれば生命保険料控除が受けられるため、税負担を軽減しながら資産運用が可能です。
オルタナティブ投資(アンティークコイン・ウイスキーなど)
オルタナティブ投資は、株式や投資信託など伝統的な投資方法とは異なる新しい投資手法のことであり、具体的には、アンティークコイン投資、ウイスキーカスク(ウイスキー樽)への投資が挙げられます。
アンティークコインは、100年以上前に発行されたコインであるため、減ることはあっても増えることはない性質から、希少性と歴史的価値によって価格が形成される資産です。世界中のコレクターの間で取引されており、長期的に価格が上昇する性質から資産運用に適しています。
ウイスキーカスクは、店舗で販売されている瓶に詰められた状態のウイスキーではなく、カスク(樽)に詰められた状態のウイスキーを保有する投資方法です。カスクのなかのウイスキーは熟成が進むため、熟成による長期的な価値の成長が期待できます。
資産としての魅力だけでなく、趣味を兼ねた投資先として世界中の愛好家から人気を集めています。伝統的な資産とは異なる値動きを期待できることから、ほかの資産と合わせて保有すれば長期投資におけるリスク分散をおこなううえでも優秀な投資方法です。
サラリーマンが資産運用する場合の注意点

サラリーマンの方が資産運用する場合の注意点を以下にまとめました。
- 投資は余剰資金の範囲内でおこなう
- 本業に支障をきたす手法で投資をしない
- 複数の投資先に投資をしてリスクを分散させる
- 確定申告が必要になる場合がある
- インサイダー取引に気をつける
- 幅広い知識を持つ専門家に相談する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
投資は余剰資金の範囲内でおこなう
投資に使用する資金は、生活費や緊急時のための資金を確保したうえで、余裕のある範囲にとどめることが基本です。生活防衛資金や数年以内に使う予定の資金を投資することは避けましょう。生活防衛資金は、半年分の生活費を余剰資金として貯蓄しておきたいところです。
生活防衛資金を確保したうえで、残りの資金を守る資産と攻める資産に分類します。守る資産と攻める資産の比率は自身のリスク許容度によって変化します。具体的に、守る資産は生活費の3カ月〜6カ月分の貯蓄にすることが望ましいです。
リスクの高い投資ばかりを選択して、許容できるリスク以上の損失を負わないように適切な資金管理を心がけましょう。リスクのバランスを考えるにあたっては、当社をはじめとする資産運用の専門家に相談することをおすすめします。
本業に支障をきたす手法で投資をしない
サラリーマンが投資をおこなう場合は、本業の勤務時間中に相場を追うようなデイトレードの売買は避けるべきです。勤務時間中にポジションが気になる投資方法は、本業に身が入らなくなり、職場のトラブルを招くかもしれません。
一般的に、投資は副業にあたらないと解釈されることが多いため、会社の規則で副業が禁止されていても、資産運用をおこなうことに問題ないケースがほとんどです。ただし、デイトレードを就業期間中におこなった場合は、社内規程や利益相反に抵触する可能性があります。
複数の投資先に投資をしてリスクを分散させる
投資の世界では「卵は一つのカゴに盛るな」という格言があります。これはカゴを落としてしまった場合に、一つのカゴに盛るとすべての卵が割れてしまうかもしれませんが、複数のカゴに分散すればほかのカゴに盛られた卵は無事であるという資産運用の王道的な例えです。
しかし、資産運用における分散について、「株式投資で複数の銘柄に分散して投資する」「株・債券・投資信託など有価証券を複数保有する」などポートフォリオによる狭い意味の分散と勘違いされるケースがあります。
資産運用における分散とは、有価証券(株・債券・投資信託)、不動産、生命保険、オルタナティブなど広い意味での分散を指します。海外積立投資のように投資先を日本だけでなく、海外を含めて分散させることも考える必要があるでしょう。
確定申告が必要になる場合がある
サラリーマンは給与所得者であるため、基本的に年末調整で税務処理を終えます。しかし、投資の利益が本業以外の所得と合わせて20万円を超えると確定申告が必要になる場合があります。
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株や投資信託を取引している場合や、NISA・iDeCoなどの非課税口座で取引している場合は、対象口座における投資の利益が20万円を超えていても確定申告の義務はありません。
正しく投資の利益にかかる税金を納められているケース、そもそも制度により税金がかからないケースでは確定申告は不要です。よって、確定申告が必要になるのは、課税される利益が一定以上発生していても正確な税金が納められていないケースになります。
確定申告を怠るとペナルティとして延滞税が発生するため、年末調整で税務処理が完了しないケースでは必ず期日までに申告するようにしてください。
インサイダー取引に気をつける
インサイダー取引は、職務上で知り得た未公表の重要情報を利用して株式などを売買する行為で、金融商品取引法で禁止されています。具体的には、社内の機密情報をもとに自社株を売買する行為が挙げられます。
勤務先の株式は、企業によっては福利厚生の一環として、社員の購入を優遇する制度が整備されている場合もあるため、購入自体が禁止されているわけではありません。しかし、積極的な売買をおこなう場合は、インサイダー取引を疑われる可能性があります。
また、銀行・保険会社などの金融商品取引業に勤めているサラリーマンは、株や債券などの有価証券の売買が禁止されています。該当する場合は、有価証券以外の投資対象への投資を検討する必要があるでしょう。
退職後も1年以内はインサイダー取引の規制対象となるため、職務上で未公表の重要情報を知る機会があるサラリーマンは取引に気をつけましょう。
幅広い知識を持つ専門家に相談する
一般的なサラリーマンは資産運用のプロではありません。知識がない状態で、独学で勉強をして情報収集するのは時間がかかるため、幅広い知識を持つ専門家に相談すると効率的です。資産運用を始めるなら中立の立場からアドバイスを受けられる、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談しましょう。
特定の金融機関に属する銀行や証券会社の担当者は、販売したい特定商品に偏った提案をすることがあります。そのため、幅広い知識を持つだけでなく、中立の立場にある専門家への相談が重要です。専門家と連携すれば、手間をかけることなく資産運用を最適化できるでしょう。
まとめ
サラリーマンの方にとって、将来の不安や生活費の上昇に備えるためにも、資産運用は必要不可欠な選択肢となりつつあります。現在の生活における負担と経済状況を踏まえると、本業以外で資産を増やす手段として資産運用を取り入れることが重要です。
投資初心者であっても、長期を前提とした方法を選ぶことで、安定して資産を形成できます。紹介したおすすめの資産運用にバランスよく投資すればリスクの分散が可能です。
ご自身のライフスタイルや資産状況に合わせて、無理のない範囲から始めてみましょう。もし、自分だけで判断するのが難しいと感じる場合は、幅広い知識を持ち、中立的なアドバイスを受けられる専門家に相談することをおすすめします。
当社では、資産運用の総合的なアドバイスをおこない、個人ではアクセスが難しい魅力的な投資先を紹介できます。プロに資産運用を適切に任せたい場合は当社にご相談ください。