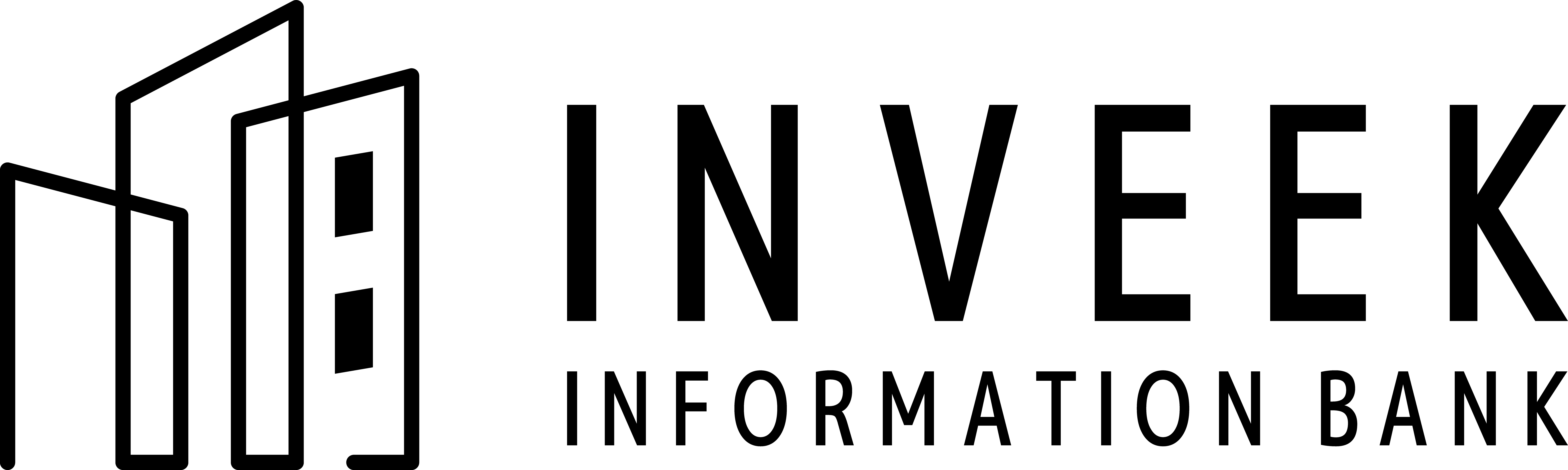初心者の方が投資を始めるにあたって投資信託とNISAは高い人気を誇っています。投資信託は金融商品ですが、NISAは税制優遇制度であるため、まったく異なる存在です。しかし、どちらも投資初心者が資産運用を効率良くおこなううえで役立つ、という点は共通しています。
本記事では、投資信託とNISAの違いを解説します。記事を読むことで、投資信託とNISAに関するさまざまな内容を把握できるようになるでしょう。
投資信託とNISAの違い

投資信託とNISAは資産運用を目的に利用する点は共通していますが、根本的な性質は異なります。投資信託は投資対象である金融商品そのものであり、NISAは税制優遇制度です。
NISAは投資信託をはじめ、非課税となる金融商品の購入枠を提供します。NISAで投資信託を購入すれば、利益に対して税金がかかりません。それぞれの概要を詳しく見ていきましょう。
投資信託の概要
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を資産運用のプロであるファンドマネージャーが運用します。専門の運用会社が株式・債券・不動産などに分散投資して運用をおこなう仕組みです。
得られた利益は、投資額に応じてすべての投資家に分配されます。
投資信託は基準価額をもとに取引されます。基準価額とは、投資信託1口あたりの時価を示す価格で、ファンドが保有する資産の総額から費用を差し引き、口数で割って算出される値のことです。
投資信託の種類は数千種類以上あり、投資対象や性質の異なるさまざまな商品が存在します。不動産を投資対象にする投資信託はREITと呼ばれ、証券取引所に上場している投資信託はETFと区別されており、同じ投資信託でも幅広い種類があります。
利益に対しては基本的には20.315%の分離課税が課される仕組みです。確定申告が必要であるかどうかは条件によって異なります。
NISAの概要
| 購入枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間の投資上限 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有総額 | 1,800万円(成長投資枠の上限は1,200万円) | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 投資対象 | 投資信託 | 投資信託、株式 |
| 買付方法 | 積立 | 一括・積立 |
NISA(Nippon Individual Savings Account)は、個人投資家向けの税制優遇制度です。通常、投資で得た利益には税金がかかりますが、NISA口座を利用して購入すると非課税で運用できます。
NISAは投資初心者でも資産運用を始めやすくすることを目的に国が設計した制度です。制度は導入以降、改正が進められ、2024年から現在の制度である新NISAが誕生しました。
現在の制度では、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの購入枠を併用できます。つみたて投資枠では、金融庁が厳選した一部の投資信託にのみ積立投資が可能です。成長投資枠では、証券会社で取り扱われているほとんどの投資信託と株式に投資できます。
年間の投資上限は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。非課税保有総額はつみたて投資枠と成長投資枠を合算して1,800万円ですが、成長投資枠の上限は1,200万円に定められています。
投資信託のメリット
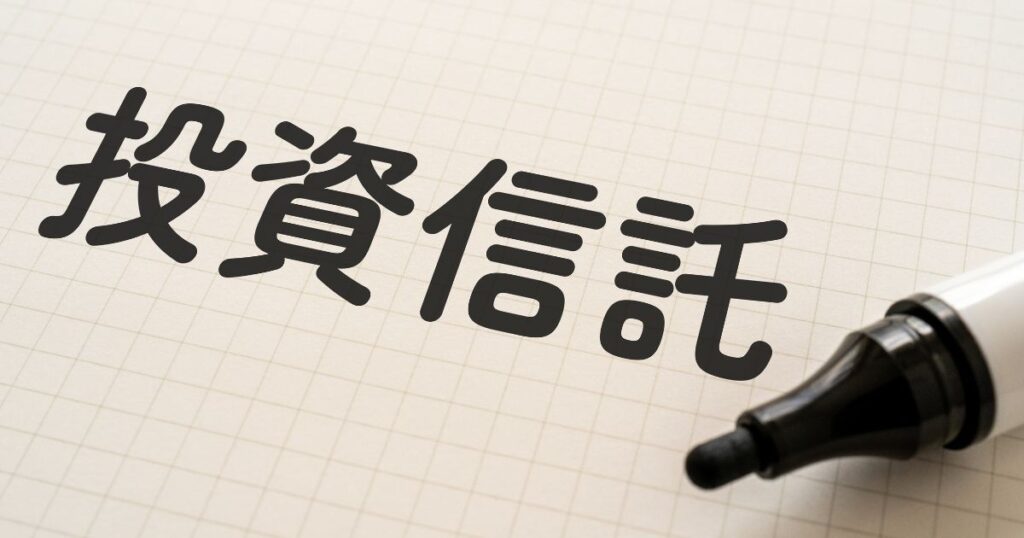
投資初心者から人気が高い投資信託のメリットを紹介します。
- 少額から投資できる
- 専門家に運用を任せられる
- 分散投資で安定した運用ができる
- 運用状況が透明でわかりやすい
- 自動積立で手間がかからない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
少額から投資できる
投資信託は1万円以下、なかには100円から購入できる商品もあります。少額から投資を始められる点が魅力です。少額投資であっても、毎月コツコツと続ける積立投資であれば、大きな成果が期待できます。
長期の投資では複利の効果が働くため、運用で得た利益を再び投資に回すことで、利益は雪だるま式に増える仕組みです。よって、長期的に安定した利益が期待できる投資信託に投資すれば、少額でも継続するほど資産は増えやすくなります。
まとまった資金を投じる一括投資は、初心者にとって心理的なハードルが高いですが、毎月1万円以下でも始められる少額投資であれば実践しやすいです。資金に余裕がない人でも始めやすいことから、年齢を問わず幅広い層から人気を集めています。
専門家に運用を任せられる
投資信託は、資産運用のプロであるファンドマネージャーに運用を任せられます。株式投資であれば、適切に運用するためには専門知識が必要であり、企業分析・経済の動向を把握するにも時間を要します。投資信託は、ファンドマネージャーが銘柄の選定・資産配分を適切におこなってくれるため、時間をかけることなく投資できるでしょう。
専門家に任せる運用は、感情に左右されにくいメリットもあります。投資に失敗する理由の多くは、市場が下落した時に焦って売却し、上昇した時に慌てて購入する感情的な判断が原因です。
専門家の運用は感情に流されることなく、一貫した運用が期待できるでしょう。
分散投資で安定した運用ができる
投資信託は、個別に株式などに投資するよりも分散投資がしやすいため、リスクを軽減しやすいメリットがあります。株式に投資する商品であれば、複数の銘柄に分散して投資をおこなうことが可能です。
一つの投資対象に資金を集中させると、値下がりした時の損失が大きくなります。しかし、複数の投資対象に資金を分散させれば、一つの投資対象が値下がりしても、資産全体に与える影響は少なくなるでしょう。
投資の基本は分散です。少額でも分散投資ができる投資信託は、資金が少なく分散投資が難しい人であっても、安定した運用が期待できます。
運用状況が透明でわかりやすい
投資信託は運用の透明性が高いことから、投資対象として信頼性があります。決算時などには行政による監査を受けており、金融庁の厳しいルールのもとで運用されています。よって、不正運用や資金流用が起こりにくい構造です。
投資家の資産は信託銀行が分別管理しているため、投資信託の運用会社が破綻した場合も投資家の資産は保全されます。制度的にも高い安全性が確保された仕組みです。
また、運用会社が定期的に運用報告書を公開しており、投資状況と運用成績を詳しく確認できます。証券会社をとおして、投資信託の基準価額と運用成績を確認できるため、投資家は詳しい情報をもとに、継続するかどうかなどの判断が可能です。
運用状況が常に開示されていることから、初心者も安心して投資できます。
自動積立で手間がかからない
投資信託は、証券会社や銀行で自動積立を設定すれば、購入に手間がかかりません。毎月一定額を投資する積立投資であれば、積立日と金額を設定するだけで、購入の自動化が可能です。
ドルコスト平均法を根拠に積立投資をおこなう場合にも、自動積立は適しています。ドルコスト平均法は、投資信託の口数を価格が高いときは少なく、安いときは多く購入する仕組みです。購入単価が平均化されるため、高値づかみのリスクを防ぎ、相場の上下を気にせずに安定したリターンが期待できるでしょう。
投資信託の自動積立は、投資のタイミングを気にする必要がなくなり、忙しい人でも続けやすくなるメリットがあります。
投資信託のデメリット

一方で、投資信託のデメリットは以下のとおりです。
- 元本割れのリスクがある
- 手数料がかかる
- 短期間で利益を狙いにくい
それぞれ詳しく解説します。
元本割れのリスクがある
投資信託への投資では、元本が保証されていません。投資した金額よりも価値が下がり、資産が減る可能性があります。株式や債券など、市場価格が変動する資産を運用対象としているため、市場の動きや経済情勢によって基準価額は日々変化します。
相場が高い時に投資信託を一括で購入し、その後に基準価額が大きく下がれば、資産が大きく減少することも。安定して運用するためには、ドルコスト平均法による積立投資がおすすめです。
投資信託は、一時的に元本割れするリスクもありますが、長期的に継続して投資すればリスクを軽減できます。
手数料がかかる
投資信託には手数料がかかります。具体的な手数料の種類と内容を以下にまとめました。
| 手数料の種類 | 内容 |
|---|---|
| 購入手数料 | 購入時に販売会社へ支払う費用 |
| 信託報酬 | 運用や管理のために毎日差し引かれる費用 |
| 信託財産留保額 | 投資信託を解約・売却する時に差し引かれる費用 |
購入手数料や信託財産留保額は、購入する投資信託によってはかからないことがあります。一方、すべての投資信託でかかる手数料が、専門家に運用を任せるために必要である信託報酬です。
信託報酬は、実質的には日割りで差し引かれる手数料であり、運用開始時には影響を与えにくいコストです。しかし、10年以上にわたって運用をする場合、信託報酬が運用成績に大きく影響することも。
信託報酬はかかることを前提に、できる限り低コストの商品を選ぶことが重要になります。
短期間で利益を狙いにくい
投資信託は、短期で大きな利益を狙う場合には向いていません。ETF(上場投資信託)と異なり、一般的な投資信託の基準価額は1日1回しか更新されず、注文をしても即時に売買できません。リアルタイムで価格が変動し、即時売買ができる株式と比較すると、短期売買には不向きです。
投資信託は、長期的な資産形成を目的とする場合は優秀な金融商品です。しかし、短期トレードなど投資の目的が異なる場合は、必ずしも適しているとは限りません。
NISAで投資信託に投資するメリット

投資信託は「金融商品」であり、NISAは「税制優遇制度」です。よって、NISAを利用して投資信託に投資をすると、以下のメリットを享受できます。
- 運用益・分配金が非課税になる
- つみたて投資枠では購入手数料がすべて無料
- 非課税期間が無期限で長期投資に最適
それぞれ詳しく見ていきましょう。
運用益・分配金が非課税になる
投資信託の主な利益は、売買によって得られる運用益であり、商品によっては分配金が出る場合もあります。NISA口座で投資信託に投資をすると、投資で得た運用益・分配金が非課税になります。
投資信託の利益には20.315%の税金がかかるため、100万円の利益が出た場合、20万3,150円が差し引かれ、79万6,850円が手元に残る計算です。しかし、NISAで投資をすれば100万円の利益をそのまま得られます。
分配金のある投資信託の場合、分配金を受け取るたびに課税されますが、NISAであれば非課税で受け取れます。分配金を再投資する際は、税金が差し引かれないため、より多くの資金を投資に回すことで、複利の効果を高められるでしょう。
つみたて投資枠では購入手数料がすべて無料
NISAのつみたて投資枠の対象になる投資信託は、購入手数料がすべて無料です。つみたて投資枠の対象商品は、金融庁が定めた基準を満たした低コストの商品に限定されています。
金融庁の基準では、共通して購入手数料が無料であるノーロード投資信託が選ばれている点が特徴です。NISAのつみたて投資枠で投資する場合、金融庁の基準を満たした優良な投資信託から選ぶことになります。
証券会社のランキングを確認し、つみたて投資枠から人気の投資信託を選ぶだけでも理想的な商品に投資しやすいでしょう。初心者にとっても、コストを抑えながら投資を始めやすい環境が整っています。
非課税期間が無期限で長期投資に最適
現行制度である新NISAでは、非課税期間が無期限に設定されているため、長期投資に適した制度となっています。従来のNISAでは非課税期間に制限があり、期間が終了すると自動的に課税口座に移されていました。
非課税期間に制限があったことは、長期投資をおこなううえで一つのハードルとなっていましたが、非課税期間が撤廃されたことで、より長期の資産形成に活用しやすい制度に生まれ変わっています。
投資信託を数十年以上保有した場合でも、非課税枠の範囲内であれば、運用益や分配金には税金がかかりません。そのため、生涯にわたる資産形成の手段としてNISAを活用できるでしょう。
10年・20年以上にわたる運用を前提にすることが多い投資信託は、非課税期間に上限がない新NISAと相性がいい仕組みとなっています。
NISAで投資信託に投資する注意点

メリットばかりに見えるNISAですが、投資信託に投資する場合、デメリットとまでとはいえないものの、以下の点に注意する必要があります。
- つみたて投資枠では商品が限られる
- 投資枠の範囲内でしか投資できない
- 損益通算ができない
それぞれ詳しく解説します。
つみたて投資枠では商品が限られる
NISAのつみたて投資枠は、金融庁が選定した一部の投資信託以外は購入できないことから、投資できる商品が限定されます。種類の多い投資信託を初心者も迷わず購入できるメリットがある一方で、投資の自由度が制限される点に注意が必要です。
投資したい投資信託がつみたて投資枠の対象でない場合は、成長投資枠を利用して投資できます。成長投資枠では、ほとんどの投資信託に投資できるため、投資対象を制限されることなく自由に運用が可能です。
つみたて投資枠で投資できる投資信託と、成長投資枠でしか投資できない投資信託を把握して購入枠を適切に使い分けるようにしましょう。
投資枠の範囲内でしか投資できない
NISAでは、年間および保有総額に非課税投資枠の上限があります。つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円であり、合計で年間360万円まで投資できます。
つみたて投資枠を利用して、投資信託を毎月一定額の投資を続ける場合、毎月10万円を超える投資額の積み立てができません。10万円を超える場合は成長投資枠で投資可能であり、合計で毎月30万円まで投資できる計算になります。
また、NISAの保有総額の上限は1,800万円です。つみたて投資枠で120万円の投資を続けた場合は15年、成長投資枠と合算した360万円を投資する場合は5年で非課税枠を使い切ることになります。
売却した場合は、翌年に保有総額の非課税枠は復活します。しかし、非課税枠の上限に到達したあとも売却せずに運用を続ける場合は、NISA以外の口座で投資する必要があるでしょう。
損益通算ができない
NISAは利益に対して税金がかからないだけでなく、損益通算の対象になりません。損益通算は、取引で生じた利益と損失を相殺して、課税される所得を減らせる制度です。
課税口座では、ある投資信託で10万円の利益を得ており、別の投資信託で10万円の損失が発生した場合は、利益と損失を相殺して課税対象となる利益をゼロにできます。NISA口座で損失が発生した場合は、損益通算の対象にならず、課税口座の利益と相殺して税金を減らせません。
損益通算の観点から、NISAは短期的にリターンを期待できるリスクの高い投資には不向きです。損益通算を前提としない、長期的な利益を期待する継続した投資への利用をおすすめします。
NISA以外で投資信託に投資する方法

非課税枠を使い切った場合に備えて、NISA以外の口座で投資する方法を3つ紹介します。
- 課税口座
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 企業型DC(企業型確定拠出年金)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
課税口座
投資信託に投資する基本的な方法は、課税口座を利用することです。課税口座は、税制優遇がない通常の投資口座のことです。課税口座には種類があるため、以下に内容をまとめました。
| 手数料の種類 | 内容 |
|---|---|
| 一般口座 | 自分で損益計算して確定申告する |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が損益計算し、て確定申告は自分でする |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が税金を自動で納付する |
課税口座で運用した場合、発生した利益に対する税金の納付が必要です。納める税金を把握するために、特定口座では証券会社が年間の損益計算をして、年間取引報告書を作成してくれます。一般口座では取引に基づいて自身で計算します。
一般口座、特定口座(源泉徴収なし)では確定申告が必要です。しかし、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、証券会社が税金を自動で納付してくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。
NISA口座を使い切ったあとに、課税口座で投資を検討している場合は、口座ごとの税金に対する対応を覚えておきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
NISA以外にも投資の非課税制度があり、その一つがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。iDeCoは、老後の資産形成を支援する制度で、毎月の掛金を自分で積み立てて投資信託を運用し、年金または一時金として受け取れます。
NISAと同様に投資信託の税金が非課税になりますが、iDeCoには複数の節税メリットがあります。投資額として拠出する毎月の掛金が全額所得控除の対象になるため、始めた瞬間から節税効果が期待可能です。
また、iDeCoの運用益を受け取る際には、退職所得控除または、公的年金等控除が適用されます。iDeCoはNISAと併用できるため、NISAの枠を超えて非課税で投資信託に投資できます。
ただし、iDeCoは職業や加入状況によって毎月の拠出上限額が異なる点に注意が必要です。拠出上限額の違いを以下にまとめました。
| 加入資格 | 条件 | 拠出限度額 |
|---|---|---|
| 第一号被保険者 | 自営業者 | 68,000円 |
| 第二号被保険者 | 会社に企業年金がない会社員 | 23,000円 |
| 企業型DCのみに加入している会社員 | 20,000円 | |
| DBと企業型DCに加入している会社員 | 20,000円 | |
| DBのみに加入している会社員 | 20,000円 | |
| 公務員 | 20,000円 | |
| 第三号被保険者 | 専業主婦(夫) | 23,000円 |
企業型DCのみに加入している会社員であれば、毎月2万円を積み立てられます。NISAのつみたて投資枠と成長投資枠をあわせると最大で毎月32万円を積み立てられる計算です。
NISA以外で投資信託を非課税で積み立てたい場合、iDeCoを利用すれば、さらに非課税枠を増やせます。ただし、いつでも売却して引き出せるNISAとは異なり、原則60歳まで引き出せない点に注意が必要です。
企業型DC(企業型確定拠出年金)
勤務している会社が企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している場合は、企業が拠出する資金で投資信託を運用できます。企業型DCは、企業が社員のために掛金を拠出し、その資金を社員自身が運用して将来の年金に備える制度です。
企業型DCに拠出される掛金は非課税になります。給与として受け取る場合は税金・社会保険料がかかるのに対して、企業型DCは実質的に社員の手取りを減らさずに老後の資産形成を効率的に進められる仕組みです。
iDeCoと同様に企業型DCで運用した投資信託の利益は非課税になります。退職所得控除・公的年金等控除の対象になることも同様です。企業型DCでは社員が上乗せで拠出できるマッチング拠出制度を利用できる場合がありますが、iDeCoと併用できないため注意が必要です。
まとめ
投資信託は、株式・債券などの投資対象に分散投資する金融商品であり、NISAは投資信託をはじめとする金融商品の利益を非課税にできる税制優遇制度です。投資信託とNISAは根本的に異なる存在ですが、共通して初心者の資産運用を支えています。
NISAを利用した投資信託への投資は、ドルコスト平均法を用いた積立投資になりますが、投資額は無理なく続けられることが前提です。最初に無理のある積立額を設定すると、継続できないことも。当社では、適切な投資額の設定を含めた一般的な資産運用のアドバイスから、投資信託以外の優れた投資対象も紹介しています。資産形成に関心のある方は、ぜひ一度当社にご相談ください。